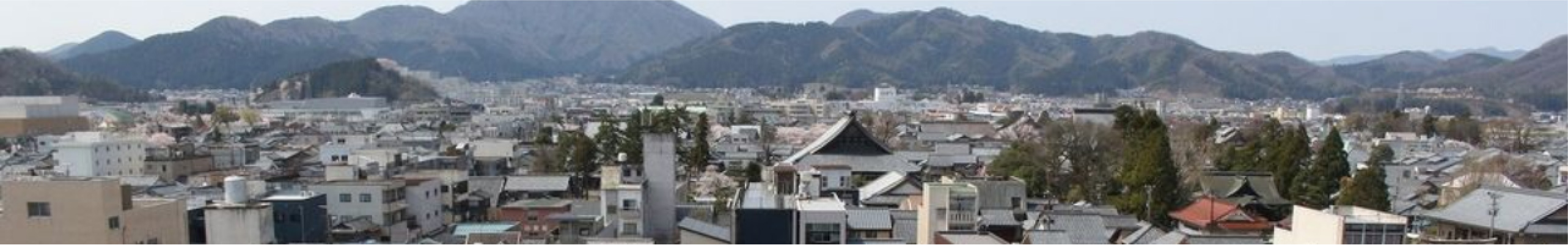最終更新日 2023年11月14日
所得と控除について(令和2年度課税まで適用)
PAGE-ID:953
所得と控除について(令和2年度課税まで適用)
※このページでは、令和2年度市民税・県民税(令和元年分所得に対する課税)まで適用される制度に基づいて一覧を記載しています。
令和3年度市民税・県民税(令和2年分所得に対する課税)から適用となる所得と控除については、こちらのページをご覧ください。→「所得と控除について(令和3年度課税から適用)」
所得について
一定期間に、個人・企業などの経済主体が勤労・事業・資産などによって得た収入から、それを得るのに要した経費を差し引いた残りの純収入のことをいいます。
| 所得の種類 | 所得金額の計算方式 | ||
|---|---|---|---|
| 総合課税 | 給与所得 | 給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額-特定支出控除=給与所得の金額(下記参照) |
| 事業所得 | 営業、農業、その他の事業をしている場合にその事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | |
| 不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | |
| 配当所得 | 株式や出資金の配当、証券投資信託の分配金など | 収入金額-その株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額 | |
| 特別徴収と申告による総合課税があります。 | |||
| 一時所得 | 賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=一時所得の金額 | |
| (注)総所得金額に算入する金額は、上記一時所得金額の2分の1の額になります。 | |||
| 雑所得 | 公的年金、個人年金、原稿料など | 次の1.2.を合計した金額=雑所得の金額 | |
| 1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(下記参照) | |||
| 2. 1.以外の雑所得の収入金額-必要経費 | |||
| 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | |
| 総合譲渡所得 | 分離譲渡以外の資産の譲渡 | 収入金額-資産の取得費用-譲渡の経費-特別控除(最高50万円)=譲渡所得の金額 | |
| (注)総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の2分の1 の額になります。(長期譲渡所得のみ)。 | |||
| 分離譲渡所得 | 土地、家屋などの資産の譲渡 | 収入金額-資産の取得費-譲渡の経費-特別控除=譲渡所得の金額 | |
| 株式等有価証券の譲渡 | 収入金額-取得費-譲渡の経費=株式譲渡所得の金額 | ||
| 特別徴収(所得税において源泉徴収を選択した口座)と申告による分離課税があります。 | |||
| 先物取引所得 | 商品先物取引による所得 |
取引による差金-経費=商品先物取引所得の金額 ※申告分離課税 |
|
| 退職所得 | 退職金、退職手当など |
(収入金額-退職所得控除)×2分の1 =退職所得の金額 ※申告分離課税 |
|
| 山林所得 | 山林(立木)を売った場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=山林所得の金額 ※申告分離課税 |
|
| 給与所得の速算表 | ||
|---|---|---|
| 給与等の収入金額の合計額 …(A) | 給与所得の金額 | |
|
(A)を4で割って千円未満切捨てた額 …(B) |
||
| から | まで | |
| 650,999円 | 0円 | |
| 651,000円 | 1,618,999円 | (A)-650,000円 |
| 1,619,000円 | 1,619,999円 | 969,000円 |
| 1,620,000円 | 1,621,999円 | 970,000円 |
| 1,622,000円 | 1,623,999円 | 972,000円 |
| 1,624,000円 | 1,627,999円 | 974,000円 |
| 1,628,000円 | 1,799,999円 | (B)×2.4 |
| 1,800,000円 | 3,599,999円 | (B)×2.8-180,000円 |
| 3,600,000円 | 6,599,999円 | (B)×3.2-540,000円 |
| 6,600,000円 | 9,999,999円 | (A)×0.9-1,200,000円 |
| 10,000,000円 | (A)-2,200,000円 | |
| 年金所得の速算表 | |||
|---|---|---|---|
| (求める所得=〔A〕×〔B〕-〔C〕) | |||
| 年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計額〔A〕 | 割合〔B〕 | 控除額〔C〕 |
| 65歳未満 | 700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。 | ||
| 700,001円~1,299,999円 | 100パーセント | 700,000円 | |
| 1,300,000円~4,099,999円 | 75パーセント | 375,000円 | |
| 4,100,000円~7,699,999円 | 85パーセント | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95パーセント | 1,555,000円 | |
| 65歳以上 | 1,200,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。 | ||
| 1,200,001円~3,299,999円 | 100パーセント | 1,200,000円 | |
| 3,300,000円~4,099,999円 | 75パーセント | 375,000円 | |
| 4,100,000円~7,699,999円 | 85パーセント | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95パーセント | 1,555,000円 | |
控除とは
一定の要件に該当することにより、所得または税額から引くことのできる金額のことです。所得控除と税額控除があります。
所得控除とは、所得金額の合計から控除できるものをいいます。所得から控除をひいたものを課税標準額といい、課税標準額に税率をかけたものが税額となります。
| 種類 | 要件 | 控除額 | 添付書類等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物的控除 | 雑損控除 |
前年中、災害等により日常生活に必要な資産に |
{(損失額+災害等関連支出額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10パーセント}又は、{災害関連支出額-5万円}のいずれか多い額 | |||
| 医療費控除 | 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合 | (支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額の5パーセントか10万円のいずれか低い額)(最高200万円) | 医療費控除の明細書 | |||
|
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) |
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、前年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC薬の購入費を支払った場合 (注)平成29年1月1日から令和3年12月31日までに支払った分が対象 |
購入費-補てん額-12,000円(最高88,000円) | セルフメディケーション税制の明細書 | |||
| 社会保険料控除 | 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払った場合 | 支払った金額 | 国民年金保険料支払証明書 | |||
| 生命保険料控除 | 前年中、平成23年12月31日までに締結された生命保険契約、介護医療保険契約および個人年金保険契約等保険金などで要件を満たすものを支払った場合 | 生命保険・個人年金保険料控除 (平成23年12月31日までに締結分) |
生命保険料(個人年金)控除証明書 | |||
| 支払額 | 控除額 | |||||
| 15,000円以下 | 全額 | |||||
| 15,001~40,000円 | 支払額の2分の1+7,500円 | |||||
| 40,001~70,000円 | 支払額の4分の1+17,500 | |||||
| 70,000円超 | 35,000円 | |||||
| 生命・個人年金保険は別々に計算 (合計の限度額70,000円) |
||||||
| 前年中、平成24年1月1日以降に締結された生命保険契約、介護医療保険契約および個人年金保険契約等保険金などで要件を満たすものを支払った場合 | 生命保険・個人年金・介護医療保険料控除 (平成24年1月1日以降締結分) |
|||||
| 支払額 | 控除額 | |||||
| 12,000円以下 | 全額 | |||||
| 12,001~ 32,000円 |
支払額の2分の1 +6,000円 | |||||
| 32,001~ 56,000円 |
支払額の4分の1 +14,000円 | |||||
| 56,000円超 | 28,000円 | |||||
| 生命・個人年金・介護医療保険は別々に計算 (合計の限度額70,000円) |
||||||
|
(注)旧契約と新契約の両方で保険料控除を受ける場合は、各保険料について旧契約・新契約それぞれ上記の式で計算し 1.旧契約保険料控除額が28,000円以下の場合 が、各保険料の控除額となります。 |
||||||
| 地震保険料控除 | 前年中、要件を満たす損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合 あるいは、要件を満たす旧長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払った場合 |
地震保険控除 | 地震保険料(旧長期損害保険料)控除証明書 | |||
| 支払額 | 控除額 | |||||
| 50,000円以下 | 支払額の2分の1 | |||||
| 50,000円超 | 25,000円 | |||||
| 長期損害保険控除 (平成18年12月31日までに締結分) |
||||||
| 支払額 | 控除額 | |||||
| 5,000円以下 | 全額 | |||||
| 5,000円超 | 支払額の2分の1 +2,500円 (最高10,000円) |
|||||
| 地震・長期損害保険控除の両方がある場合、それぞれの控除の合計金額が控除額となります (最高25,000円) |
||||||
| 小規模企業共済等掛金控除 | 前年中、小規模企業共済(旧第2種共済を除く)掛金、確定拠出年金法の個人型・企業型年金加入者掛金および心身障害者扶養共済掛金を支払った場合 | 支払った金額 | ||||
| 以下は、前年12月31日の現況でとらえます。ただし、年の途中で死亡した時は死亡した日の現況でとらえます。 | ||||||
| 種類 | 要件 | 控除額 | 添付書類等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人的控除 | 障 害 者 控 除 |
本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合 | 普通障害者は26万円 | 障害者手帳の提示もしくは福祉事務所長の障害者認定証明書 | ||
| 特別障害者は30万円 | ||||||
| (本人以外で同居の特別障害者を扶養している場合は23万円加算) | ||||||
| 寡 婦 控 除 |
1.夫と死別・離婚した後再婚していない人で扶養親族や生計を一にしている総所得金額等が38万円以下の子がある人 | 26万円 | ||||
| 2.夫と死別した後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人 | ||||||
| 特別寡婦控除 | 上記の1.に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限ります。)に該当し、かつ合計所得金額が500万円以下の人 | 30万円 | ||||
| 寡 夫 控 除 |
妻と死別(離婚)した後再婚していない人で生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子があり、かつ合計所得金額が500万円以下である人 | 26万円 | ||||
| 勤労学生控除 | 前年中、自己の勤労に基づく給与所得等が有り、合計所得金額が65万円以下で、そのうち自己の勤労によらない所得の合計額が10万円以下の場合 | 26万円 | ||||
| 配 偶 者 控 除 |
本人の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が38万円以下の場合 (税金上の配偶者には、内縁の配偶者は含まれません) →詳細はこちらのページ参照 |
一般の配偶者 11万円から33万円 (別表参照) |
||||
| 老人(70歳以上)の配偶者 13万円から38万円 (別表参照) |
||||||
| 配偶者特別控除 | 本人の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合 (税金上の配偶者には、内縁の配偶者は含まれません) |
納税者本人の合計所得・配偶者の前年中の合計所得金額に応じて1万円から33万円まで (別表参照) |
||||
| 扶 養 控 除 |
生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合 |
一般 33万円 (注)16歳以上19歳未満又は23歳以上70歳未満の人 |
||||
| 特定の扶養親族 45万円 (注) 特定:19歳以上23歳未満の人 |
||||||
| 老人の扶養親族 (注) 70歳以上の人 |
||||||
| 同居老親等以外 38万円 | ||||||
| 同居老親等 45万円 | ||||||
| 基礎控除 | すべての納税義務者 | 33万円 | ||||
| 配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額 | ||
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
| 一般の配偶者 38万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 老人の配偶者(70歳以上) 38万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
税額控除とは上記の課税標準額で出した税額から控除するもののことをいいます。
|
控除の種類 |
控除内容 |
該当要件および控除額計算 |
|---|---|---|
| 寄附金税額控除 |
以下に該当する寄附金がある場合、一定の金額が市・県民税の所得割の金額から税額控除される ・都道府県・市区町村への寄附金(いわゆる「ふるさと納税」) |
「寄附金-2,000円」×10パーセントを所得割から税額控除(市民税6パーセント、県民税4パーセント) (支払った寄附金の合計額は総所得金額等の30パーセントを上限) |
| (注)特例控除(ふるさと納税の場合) 「地方公共団体への寄附金-2,000円」×「90パーセント-0~45パーセント(所得税の税率)×1.021」を税額控除 (注)特例控除は所得割の20パーセントを上限 |
||
| 配当控除 | 株式等の配当所得があり、確定申告で総合課税を選択した場合、その金額に定められた割合を乗じた金額が控除される | 別表参照 |
| 配当割又は株式等譲渡所得割額控除 | 一定の配当や上場株式等所得については、他の所得と区分して市・県民税5%が課税されており、申告不要となっているが、申告した場合は所得割で課税され、配当割額又は株式等譲渡所得割額が控除される | 市民税 配当割額又は株式等譲渡所得割の5分の3 県民税 配当割額又は株式等譲渡所得割の5分の2 |
| 調整控除 | 税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)の差額による負担増を調整するため、所得割額から一定の金額が控除される | 1. 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合、下記のいずれか小さい額の5% (イ)人的控除額の差の合計額 (ロ)個人住民税の課税所得金額 2. 個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合 { 人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5パーセント ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とする。 (注)人的控除の差については別表参照 |
| 住宅借入金等特別税額控除 (住宅ローン控除) |
所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額が控除される | |
|
下記のいずれか少ない金額を控除 1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 2.
|
| 種類 | 人的控除の差 | 所得税 | 住民税 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害者控除 | 普通障害者 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | ||
| 特別障害者 | 同居以外 | 10万円 | 40万円 | 30万円 | ||
| 同居 | 22万円 | 75万円 | 53万円 | |||
| 寡婦控除 | 一般寡婦 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | ||
| 特別寡婦 | 5万円 | 35万円 | 30万円 | |||
| 寡夫控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |||
| 勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |||
| 配偶者控除 | 一般 配偶者 |
納税義務者の 合計所得金額 900万円以下 |
5万円 | 38万円 | 33万円 | |
| 納税義務者の 合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
4万円 | 26万円 | 22万円 | |||
| 納税義務者の 合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
2万円 | 13万円 | 11万円 | |||
| 老人 配偶者 |
納税義務者の 合計所得金額 900万円以下 |
10万円 | 48万円 | 38万円 | ||
| 納税義務者の 合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
6万円 | 32万円 | 26万円 | |||
| 納税義務者の 合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
3万円 | 16万円 | 13万円 | |||
| 配偶者 特別控除 |
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
|
納税義務者の 合計所得金額 900万円以下 |
5万円 | 38万円 | 33万円 |
| 納税義務者の 合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
4万円 | 26万円 | 22万円 | |||
| 納税義務者の 合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
2万円 | 13万円 | 11万円 | |||
40万円超 45万円未満 |
納税義務者の 合計所得金額 900万円以下 |
3万円 ※1 |
38万円 | 33万円 | ||
| 納税義務者の 合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
2万円 ※2 |
26万円 | 22万円 | |||
| 納税義務者の 合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
1万円 ※3 |
13万円 | 11万円 | |||
| 45万円超 123万円未満 |
納税義務者の 合計所得金額 900万円以下 |
適用なし ※4 |
- | - | ||
| 納税義務者の 合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
||||||
| 納税義務者の 合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
||||||
| 扶養控除 | 一般扶養 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | ||
| 特定扶養 | 18万円 | 63万円 | 45万円 | |||
| 老人扶養 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |||
| 同居老親等 | 13万円 | 58万円 | 45万円 | |||
| 基礎控除 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |||
※1 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(市・県民税33万円、所得税36万円)
※2 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の2の差額(市・県民税22万円、所得税24万円)
※3 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の1の差額(市・県民税11万円、所得税12万円)
※4 税制改正後に新たに控除の適用を受けるため、控除差額を起因とする新たな負担増が生じることがないことから、調整控除の対象となりません。