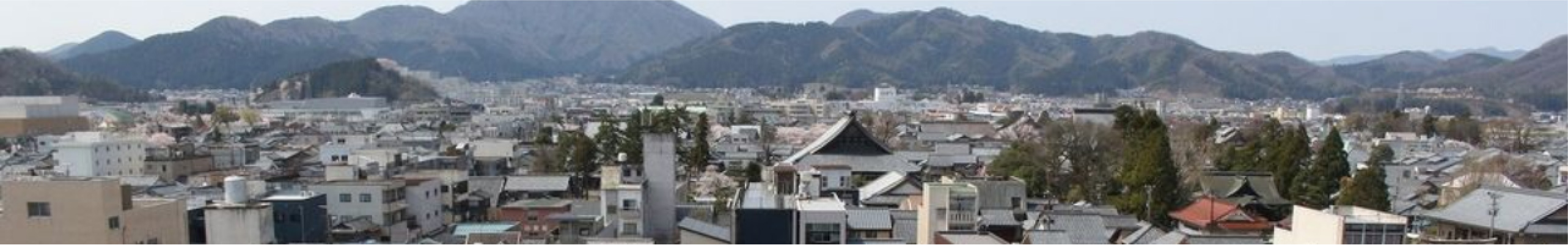最終更新日 2024年8月6日
サービスの種類(要支援1・要支援2の人が受けられるサービス)
PAGE-ID:124
要支援1・要支援2と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。
介護保険の介護予防サービスは、地域包括支援センターが中心となってサポートします。
地域包括支援センターは、高齢者の福祉や介護についての相談、権利擁護のための事業などを行う窓口です。介護が必要になる可能性がある人などのための予防プランづくりも行います。
(注)指定事業所一覧
介護予防サービス
自宅で利用できるサービス
1.訪問型サービス(総合事業)
ホームヘルパーやNPO職員、地域住民、リハビリ専門職員などが訪問し、身体介護や生活援助、リハビリをおこないます
利用者以外のための家事、金銭・貴重品の取り扱い、医療行為は利用できません
2.訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに、浴槽を積んだ入浴車と専門職員が訪問し入浴の介助を行います
3.介護予防訪問看護
医師の指示に基づき看護師等が訪問し療養上の世話などを行います
4.介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士等が訪問し、機能回復訓練を行います
5.介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し療養上の管理や指導を行います
施設に通って利用するサービス
6.通所型サービス(総合事業)
通所介護施設、または地域の公共施設等に通い、食事や入浴、日常動作訓練を行ったり、レクリエーションや運動を行います。
7.介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護施設等に通い、心身機能の維持回復を図るため、機能訓練などを日帰りで行います
8.介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護施設に短期間宿泊しながら、食事や入浴などの日常生活の介護を受けることができます
9.介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
家庭で療養している高齢者などが介護施設に短期間宿泊しながら、介護や機能訓練を受けることができます
選択的サービス
介護予防通所介護、介護予防リハビリテーションの中で、選択的サービスとして、「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」を組み合わせて利用できます
「運動器の機能向上」
理学療法士等の指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います
「栄養改善」
管理栄養士が、低栄養を予防するための食べ物や、食事作りや食材購入方法の指導、情報提供などを行います
「口腔機能の向上」
歯科衛生士等が、歯磨きや義歯の手入れ法の指導や、摂食・えん下機能を向上させる訓練などを行います
その他の居宅サービス
10.介護予防福祉用具貸与
歩行器などの福祉用具を貸与(レンタル)します
11.特定介護予防福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を県の指定を受けた事業者から購入したとき、その購入費を支給します 【年間10万円を上限に費用の9割(一定の所得以上の方は8割もしくは7割)を支給】
マイナポータルでの申請はこちら
12.介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に費用の9割(一定の所得以上の方は8割もしくは7割)を支給します
※住宅改修に着工する前に、事前申請が必要です
地域密着型サービス
13.介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です
要支援1の人は利用できません
14.介護予防認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です
15.介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します