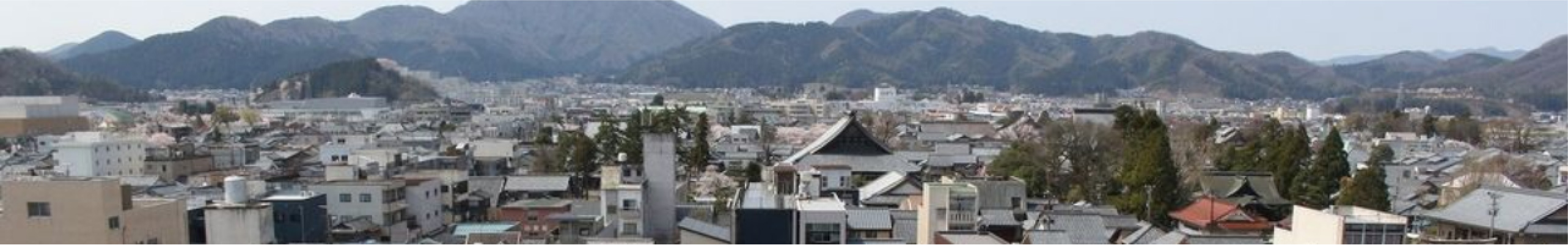最終更新日 2025年4月24日
介護保険料
PAGE-ID:6168
介護保険料について
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険者ごとの計算方法により決められ、医療保険料と一括して納入します。(詳しくは、加入している医療保険者にご確認ください。)
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、市が介護保険のサービスに必要な費用などから算出した「基準額」をもとに、所得などに応じて決定しています。
年度途中で65歳になる人は、65歳の誕生日の前日の属する月(1日生まれの人は前月)から越前市へ介護保険料を納めていただくことになります。
令和6年度から65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料を改定しました
介護保険は国や都道府県、市区町村が負担する公費(50%)と、40歳以上の方が納める介護保険料(50%)を財源として運営されています。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料(50%のうち23%を負担)について、3年ごとに策定する介護保険事業計画(第9期:令和6年度から令和8年度)に基づき、3年を通じて財政の均衡が保たれるよう改定を行いました。
基準額(第5段階)の引き上げはありません。
所得区分を12段階から国が示す13段階に変更しました。
段階ごとの保険料は下表のとおりです。
市独自の取り組みとして、低所得者層の負担を軽減しました。
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
| 所得段階 | 区 分 | 負担割合 | 1年間の保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受けている人 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人 |
基準額×0.25 | 17,670円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超120万円以下の人で、かつ、第1段階に該当しない人 | 基準額×0.485 | 34,280円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人で、かつ、第1段階に該当しない人 | 基準額×0.685 | 48,410円 |
| 第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、かつ、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人 | 基準額×0.85 | 60,070円 |
| 第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、かつ、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超の人 | 基準額 | 70,680円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 84,810円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 91,880円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 106,020円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 120,150円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 134,290円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上の620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 148,420円 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上の720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 162,560円 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 169,630円 |
市民税非課税:市民税の所得割・均等割ともに非課税
合計所得金額:地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額
課税年金収入額:公的年金等の収入額(遺族年金等の非課税年金収入は含みません)
保険料の納め方
原則として、年金からの天引きで納めていただきます。
介護保険料は、年金からの天引き(特別徴収)が原則です。しかし、年金の種類や年金額、そのほかの理由により天引きができない人は、納付書(普通徴収)で納めていただくことになります。
年金から天引きできない場合(主な例)
- 年金の年額が18万円未満の場合
- 年度途中で65歳になられた場合
- 年度途中で越前市に転入された場合
- 4月1日時点で年金を受けていなかった場合
納付方法
特別徴収(年金からの天引き)の人
年金の支給時(年6回)に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収(納付書)の人
7月に送付する「介護保険料決定通知書」に同封されている納付書で越前市収納金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリまたは税務課窓口で納めてください。
納付期限は、7月から翌年2月までの毎月月末になります。(年8回)
- 越前市収納金融機関:福井銀行 北陸銀行 福邦銀行 北國銀行 福井信用金庫 北陸労働金庫 越前たけふ農業協同組合 福井県農業協同組合(ゆうちょ銀行については納付書で納めていただくことは出来ませんが、口座振替のみ利用できます。)
- 7月以降に65歳になられたり、転入された方については「介護保険料決定通知書」が送られて以降の納付期限までに納めていただくことになりますので、納付回数が8回より少なくなります。
介護保険適用除外施設に入所されている方は介護保険料の納付が不要です
介護保険適用除外施設に入所されている方は介護保険料の納付が不要になります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は医療保険者に届出が必要です。第1号被保険者(60歳以上の方)は届出不要です。
詳しくはこちら介護保険の適用除外になる場合