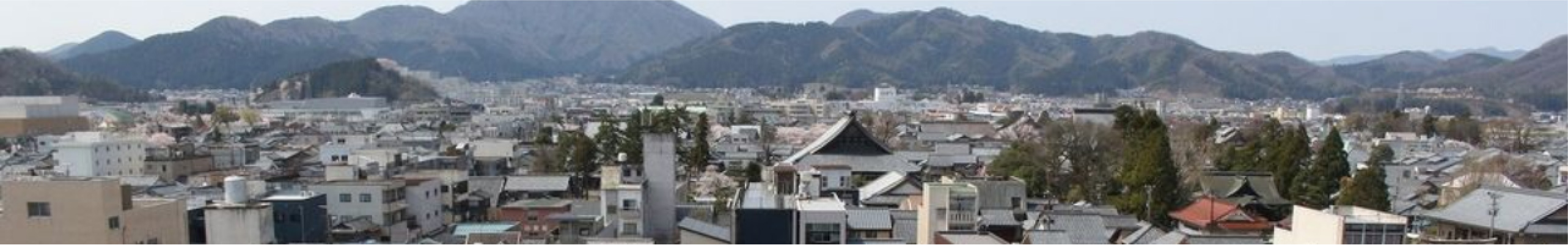最終更新日 2024年6月16日
文化財種別一覧
PAGE-ID:1004
種別一覧
建造物15件
|
指定区別 |
種別 | 名 称 | 時代 | 数量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 建造物 | 旧谷口家住宅 (きゅうたにぐちけじゅうたく) | 江戸末期 | 1棟 | 余川町 越前の里 | 昭和52年 1月28日 |
| 国 | 建造物 | 大塩八幡宮拝殿 (おおしおはちまんぐうはいでん) | 室町後期 | 1棟 | 国兼町 | 昭和53月 5月31日 |
| 国 | 建造物 | 大滝神社本殿及び拝殿 同附書 (おおたきじんじゃはいでんおよびはいでんどうふしょ) |
江戸(天保14年) | 大滝町 | 昭和59年 5月21日 | |
| 県 | 建造物 |
二階堂白山神社本殿および拝殿 |
本殿:江戸中期 拝殿:文久3年(1863年) |
2棟 | 二階堂町 | 平成29年3月31日 |
| 市 | 建造物 | 石造 無縫塔 (せきぞう むほうとう) | 室町 | 1基 | 土山町 | 昭和49年11月 1日 |
| 市 | 建造物 | 石造 宝篋印塔 (せきぞう ほうきょういんとう) | 室町 | 1基 | 土山町 | 昭和49年11月 1日 |
| 市 | 建造物 | 石造 宝篋印塔(附・石室・石幢) (せきぞうほうきょういんとう つけたり せきしつ・せきどう) |
江戸初期 | 1基 | 京町二丁目 | 昭和58年11月 1日 |
| 市 | 建造物 | 石造 層塔 (せきぞう そうとう) | 鎌倉末期 | 1基 | 中津山町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 建造物 | 石造 八角石塔 (せきぞう はっかくせきとう) | 南北朝 | 1基 | 別印町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 建造物 | 大滝神社奥の院本殿 (おおたきじんじゃおくのいんほんでん) |
江戸中期 | 1棟 | 大滝町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 建造物 | 奥の院岡太神社本殿 (おくのいんおかもとじんじゃほんでん) |
江戸初期 | 1棟 | 大滝町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 建造物 | 成願寺(本堂、山門、経蔵、内観音堂、鐘楼、庫裏)(じょうがんじ)(ほんどう、さんもん、きょうぞう、うちかんのんどう、しょうろう、くり) | 江戸時代 | 6棟 | 岩本町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 建造物 | 旧府中城表門(正覚寺山門) (きゅうふちゅうじょうおもてもん しょうがくじさんもん) |
江戸後期 | 1棟 | 京町二丁目 | 平成13年12月 5日 |
| 市 | 建造物 | 五皇神社楼門 (ごおうじんじゃろうもん) | 幕末から明治前期(推定) | 1棟 | 文室町 | 平成25年1月25日 |
| 市 | 建造物 |
山田家石廟及び石殿 附 石板浮彫仏像一枚(石廟)・木造荼枳 尼天像一躯(石殿)・石柵付基壇一基 |
伝・江戸後期 | 2棟 | 粟田部町 |
平成25年1月25日
|
絵画 45件
| 指定区別 | 種別 | 名 称 | 時代 | 数量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 絵画 |
紙本著色源氏物語図六曲屏風 |
江戸初期 | 半双 | 新堂町 | 昭和63年3月18日 |
| 県 | 絵画 | 紙本著色峨山韶碩像 (しほんちゃくしょく がざんじょううせきぞう) | 南北朝 | 1幅 | 深草一丁目 | 平成 3年 9月10日 |
| 県 | 絵画 | 紙本著色 野郎歌舞伎図屏風 (しほんちゃくしょく やろうかぶきずびょうぶ) | 江戸初期 | 6曲1隻 | 本町 | 平成22年4月9日 |
| 県 | 絵画 | 紙本著色 結城秀康像 (しほんちゃくしょく ゆうきひでやすぞう) | 江戸初期 | 1幅 | 本町 | 平成23年3月 25日 |
| 県 | 絵画 | 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 (しほんちゃくしょく あみださんぞんらいごうず) | 鎌倉時代 | 1幅 | 粟田部町 | 平成27年3月31日 |
| 県 | 絵画 | 紙本金地著色 千鳥図六曲屏風 (しほんきんじちゃくしょく ちどりずろっきょくびょうぶ) | 江戸初期 | 6曲1双 | 武生公会堂記念館 | 平成28年3月25日 |
| 県 | 絵画 | 紙本著色 本多吉松丸像 (しほんちゃくしょく っほんだよしまつまるぞう) | 江戸初期 | 1幅 | 京町二丁目 | 平成28年3月25日 |
| 県 | 絵画 | 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 (けんぽんちゃくしょく あみださんぞんらいごうず) | 南宋時代 | 1幅 | 京町二丁目 | 平成29年3月31日 |
| 県 | 絵画 | 紙本金地著色 祭礼図絵馬 しほんきんじちゃくしょくさいれいずえま | 江戸前期(寛文3年) | 1面 | 大滝町 | 平成30年3月30日 |
| 県 | 絵画 | 板地著色 大瀧児大権現祭礼図絵馬 いたじちゃくしょくおおたきちごだいごんげんさいれいずえま | 江戸後期(天保5年) | 1面 | 大滝町 | 平成30年3月30日 |
| 県 | 絵画 | 絹本著色 地蔵十王図 (けんぽんちゃくしょく じぞうじゅうおうず) | 鎌倉後期 | 1幅 | 蓬莱町 | 平成31年3月22日 |
| 県 | 絵画 | 紺絹金泥種子両界曼荼羅図(こんけんきんでいしゅじりょうかいまんだらず) | 鎌倉から南北朝 | 2幅 | 住吉町 | 令和4年8月2日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 光明号本尊 (けんぽんちゃくしょく こうみょうごうほんぞん) | 室町末期 | 1幅 | 清水頭町 | 昭和44年11月 1日 |
| 市 | 絵画 | 紙本著色 山越阿弥陀図 (しほんちゃくしょく やまごえあみだず) | 室町末期 | 1幅 | 横市町 | 昭和44年11月 1日 |
| 市 | 絵画 | 紙本著色 結城秀康・土屋左典厩・永見右金吾像 (しほんちゃくしょく ゆうきひでやす・つちやさてんきゅう・ながみうきんごぞう) |
江戸初期(慶長12年) | 1幅 | 深草一丁目 | 昭和44年11月 1日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 十六善神図 (けんぽんちゃくしょく じゅうろくぜんしんず) | 鎌倉 | 1幅 | 府中三丁目 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 十六羅漢図 (けんぽんちゃくしょく じゅうろくらかんず) | 室町 | 16幅 | 京町二丁目 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 仏涅槃図 (けんぽんしゃくしょく ぶつねはんず) | 桃山 | 1幅 | 本町 | 昭和53年11月 1日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 仏涅槃図 (けんぽんちゃくしょく ぶつねはんんず) | 桃山 | 1幅 | 京町二丁目 | 昭和55年11月 1日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 阿弥陀如来像 (けんぽんちゃくしょく あみだにょらいぞう) | 室町初期 | 1幅 | 府中三丁目 | 昭和59年11月 1日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 不動明王図(青不動・黄不動) (けんぽんちゃくしょく ふどうみょうおうず)(あおふどう・きふどう) | 鎌倉から室町 | 2幅 | 府中三丁目 | 昭和60年11月 1日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 弁財天曼荼羅図 (けんぽんちゃくしょく べんざいてんまんだらず) | 室町末期 | 1幅 | 大滝町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 地蔵十王図 (けんぽんちゃくしょく じぞうじゅうおうず) | 室町末期 | 1幅 | 大滝町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 薬師如来像 (けんぽんちゃくしょく やくしにょらいぞう) | 鎌倉 | 1幅 | 大滝町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 仏涅槃図 (けんぽんちゃくしょく ぶつねはんず) | 桃山 | 1幅 | 粟田部町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 山越阿弥陀図 (けんぽんちゃくしょく やまごえあみだず) | 室町 | 1幅 | 粟田部町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 方便法身尊像 (けんぽんちゃくそく ほうべんほっしんぞんぞう) | 室町後期 | 1幅 | 粟田部町 | 昭和62年 9月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 方便法身尊像 けんぽんちゃくしょく ほうべんほっしんそんぞう | 室町後期 | 1幅 | 新堂町 | 昭和62年 9月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 (けんぽんちゃくしょく あみださんぞんらいごうず) | 鎌倉末期 | 1幅 | 粟田部町 | 昭和62年 9月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 (けんぽんちゃくしょく あみださんぞんらいごうず) | 鎌倉末期 | 1幅 | 岩本町 | 昭和62年 9月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 阿弥陀来迎図 (けんぽんちゃくしょく あみだらいごうず) | 室町 | 1幅 | 岩本町 | 昭和62年 9月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 十二天曼荼羅図 (けんぽんちゃくしょく じゅうにてんまんだらず) | 室町初期 | 1幅 | 粟田部町 | 昭和62年 9月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 十三仏図 (けんぽんちゃくしょく じゅうさんぶつず) | 室町初期 | 1幅 | 岩本町 | 昭和62年 9月12日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 (けんぽんちゃくしょく あみださんぞんらいごうず) | 鎌倉末期 | 1幅 | 京町二丁目 | 昭和62年11月 2日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 二十五菩薩来迎図 (けんぽんちゃくしょく にじゅうごぼさつらいごうず) | 鎌倉末期 | 1幅 | 京町二丁目 | 昭和62年11月 2日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 仏涅槃図 (けんぽんちゃくしょく ぶつねはんず) | 南北朝 | 1幅 | 深草一丁目 | 昭和63年11月 1日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 善導大師像 (けんぽんちゃくしょく ぜんどうだいしぞう) | 室町 | 1幅 | 本町 | 平成19年4月16日 |
| 市 | 絵画 | 紙本著色 源氏物語図屏風 (しほんちゃくしょく げんじものがたりずびょうぶ) | 桃山 | 6曲1双 | 京町一丁目 | 平成21年12月25日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 当麻曼荼羅図 (けんぽんちゃくしょく たいままんだらず) | 江戸(享保6年) | 1幅 | 京町二丁目 | 平成23年11月11日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 釈迦十六善神図 (けんぽんちゃくしょく しゃかじゅうろくぜんしんず) | 鎌倉から南北朝 | 1幅 | 京町二丁目 | 平成23年11月11日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 阿弥陀三尊来迎図 けんぽんちゃくしょく あみださんぞんらいごうず | 鎌倉 | 1幅 | 粟田部町 | 平成31年3月11日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 蓮如・善鎮連坐像 けんぽんちゃくしょく れんにょ・ぜんちんれんざぞう | 桃山 | 1幅 | 本町 | 令和2年3月16日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 准如像 けんぽんちゃくしょく じゅんにょぞう | 江戸 | 1幅 | 本町 | 令和2年3月16日 |
| 市 | 絵画 | 絹本著色 五師連坐像 けんぽんちゃくしょく ごしれんざぞう | 江戸 | 1幅 | 本町 | 令和3年8月10日 |
| 市 | 絵画 | 紙本著色 源氏物語図屏風 しほんちゃくしょく げんじものがたりずびょうぶ | 江戸 | 六曲一双 | 不老町 | 令和6年4月11日 |
彫刻 89件
| 指定区別 | 種別 | 名 称 | 時代 | 数量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 彫刻 | 木造 男神坐像(伝天津日高日子穗穗出見命)木造 男神坐像(伝 塩 椎 神) (もくぞうだんしんざぞう)(てんあまつひこひこほほでみのみと)(もくぞうだんしんざぞう)(でんしおづちのかみ) | 平安後期 | 2躯 | 大虫町 | 平成 6年 6月28日 |
| 県 | 彫刻 | 木造 十王像 (もくぞう じゅうおうず) | 室町から江戸 | 13躯 | 朽飯町 | 昭和45年 5月 8日 |
| 県 | 彫刻 | 木造 十一面観音菩薩立像 (もくぞう じゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう) | 平安末期 | 1躯 | 東庄境町 | 昭和45年 5月 8日 |
| 県 | 彫刻 | 木造 虚空蔵菩薩坐像 (もくぞう こくうぞうぼさつざぞう) | 平安前期 | 1躯 | 大滝町 | 昭和63年 3月18日 |
| 県 | 彫刻 | 木造 聖観音菩薩立像 (もくぞう しょうかんのんぼさつりゅうぞう) | 平安末期 | 1躯 | 荒谷町 | 平成 3年 9月10日 |
| 県 | 彫刻 | 木造 伝薬師如来坐像 (もくぞう でんやくしにょらいざぞう) | 10世紀末 | 1躯 | 西谷町 | 平成 3年 9月10日 |
| 県 | 彫刻 | 木造 千手観音菩薩立像 (もくぞう せんじゅかんのんぼさつりゅうぞう) | 11世紀中頃 | 1躯 | 余川町 | 平成 8年 5月 31日 |
| 市 | 彫刻 | 引接寺石仏群 (いんじょうじせきぶつぐん) | 室町末期 | 25躯 | 京町三丁目 | 昭和44年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 石造 地蔵菩薩立像 (せきぞう じぞうぼさつりゅうぞう) | 室町末期 | 1躯 | 南三丁目 | 昭和44年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 石造 不動明王立像 (せきぞう ふどうみょうおうりゅうぞう) | 室町末期 | 1躯 | 南三丁目 | 昭和44年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 徳川家康坐像 (もくぞう とくがわいえやすざぞう) | 江戸初期 | 1躯 | 深草一丁目 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 徳川秀忠坐像 (もくぞう とくがわひでただぞう) | 江戸初期 | 1躯 | 深草一丁目 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 結城秀康坐像 (もくぞう ゆうきひでやすざぞう) | 江戸初期 | 1躯 | 深草一丁目 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 峨山韶碩坐像 (もくぞう がざんじょうせきざぞう) | 江戸初期 | 1躯 | 深草一丁目 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 通幻寂霊坐像 (もくぞう つうげんじゃくれいざぞう) | 室町中期 | 1躯 | 深草一丁目 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 舜国洞授坐像 (もくぞう しゅんこくどうじゅざぞう) | 江戸初期 | 1躯 | 深草一丁目 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 十一面観音菩薩坐像 (もくぞう じゅういちめんかんのんぼさつぞう) | 平安末期 | 1躯 | 御幸町 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 聖観音菩薩坐像 (もくぞう しょうかんのんぼさつざぞう) | 平安 | 1躯 | 池泉町 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 銅造 阿弥陀如来立像 (どうぞう あみだにょらいりゅうぞう) | 鎌倉後期 | 1躯 | 京町二丁目 | 昭和47年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 豊磐窓命坐像 木造 櫛磐窓命坐像 (もくぞう とよいわまどのみことざぞう もくぞう くしいわまどのみことざぞう) | 室町末期 | 2躯 | 国兼町 | 昭和48年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 釈迦如来坐像 (もくぞう 釈迦みょらいざぞう) | 室町 | 1躯 | 深草一丁目 | 昭和48年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 文殊菩薩坐像・普賢菩薩坐像 木造 文殊菩薩坐像(・ふげんぼさつざぞう) | 江戸初期 | 2躯 | 深草一丁目 | 昭和48年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 獅子頭 (もくぞう ししがしら) | 室町末期 | 1面 | 京町一丁目 | 昭和48年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来坐像(もくぞう あみだにょらいざぞう) | 平安 | 1躯 | 中平吹町 | 昭和49年11月1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 大日如来坐像 (もくぞう だいにちにょらいざぞう) | 平安 | 1躯 | 中平吹町 | 昭和49年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 十一面観音菩薩立像 (もくぞう じゅういちめんかんのんりゅうぞう) | 室町末期 | 1躯 | 京町三丁目 | 昭和50年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 天神坐像 (もくぞう てんじんざぞう) | 室町 | 1躯 | あおば町 | 昭和50年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 聖観音菩薩坐像 (もくぞう しょうかんのんぼさつざぞう) | 南北朝 | 1躯 | 高瀬一丁目 | 昭和51年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 薬師如来坐像 (もくぞう やくしにょらいざぞう) | 平安末期 | 1躯 | 蓑脇町 | 昭和52年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 四天王立像 (もくぞう してんのうりゅうぞう) | 平安末期 | 3躯 | 入谷町 | 昭和52年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 千手観音菩薩立像 (もくぞう せんじゅかんのんりゅうぞう) | 平安末期 | 1躯 | 池泉町 | 昭和53年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 四天王立像 (もくぞう してんのうりゅうぞう) | 平安末期 | 4躯 | 池泉町 | 昭和53年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 天部立像 (もくざう てんぶりゅうぞう) | 平安末期 | 2躯 | 蓑脇町 | 昭和54年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 昌庵こうほう坐像 (もくぞう しょうあんこうほうざぞう) | 江戸初期 | 1躯 | 春日野町 | 昭和54年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 天部立像 (もくぞうてんぶりゅうぞう) | 平安後期 | 1躯 | 中居町 | 昭和55年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 薬師如来坐像 (もくぞう やくしにょらいざぞう) | 平安末期 | 1躯 | 不老町 | 昭和59年8月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来坐像 (もくぞう あみだにょらいざぞう) | 平安末期 | 1躯 | 不老町 | 昭和59年8月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 持国天立像 (もくぞう じこくてんりゅうぞう) | 平安 | 1躯 | 不老町 | 昭和59年8月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 多聞天立像 (もくぞう たもんてんりゅうぞう) | 平安 | 1躯 | 不老町 | 昭和59年8月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 薬師如来坐像 (もくぞう やくしにょらいざぞう) | 平安末期 | 1躯 | 下中津原町 | 昭和60年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 |
木造 十一面観音菩薩立像 (もくぞう じゅういちめんかのんぼさつりゅうぞう) |
平安 | 1躯 | 西樫尾町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 十一面観音菩薩立像 (もくぞう じゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう) | 平安末期 | 1躯 | 西樫尾町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 泰澄大師坐像 (もくぞう たいちょうだいしざぞう) | 鎌倉 | 1躯 | 西樫尾町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 地蔵菩薩立像 (もくぞう じぞうぼさつりゅうぞう) | 平安中期 | 1躯 | 粟田部町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 毘沙門天立像 (もくそう びしゃもんてんりゅうぞう) | 平安 | 1躯 | 粟田部町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来坐像 (もくぞう あみだにょらいざぞう) | 平安後期 | 1躯 | 大滝町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 薬師如来坐像 (もくぞう やくしにょらいざぞう) | 平安末期 | 1躯 | 大滝町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 薬師如来坐像 (もくぞう やくしにょらいざぞう) | 平安中期 | 1躯 | 岩本町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 薬師如来坐像 (もくぞう やくしにょらいざぞう) | 平安後期 | 1躯 | 杉尾町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 十一面観音菩薩立像 (もくぞう じゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう) | 平安中期 | 1躯 | 山室町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 聖観音菩薩立像 (もくぞう しょうかんのんぼさつりゅうぞう) | 平安中期 | 1躯 | 領家町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 聖観音菩薩立像 (もくぞう しょうかんのんぼさつりゅうぞう) | 平安中期 | 1躯 | 室谷町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 女神坐像 (もくぞう めがみざぞう) | 鎌倉 | 1躯 | 南中町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 能面 鬼神(悪尉) (のうめん きじん)(あくじょう) | 鎌倉 | 1面 | 大滝町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 能面 翁(黒色尉)(のうめん おきな)(こくしょくじょう) | 室町 | 1面 | 定友町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 能面 翁 (のうめん おきな) | 室町 | 1面 | 定友町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 能面 飛出(三光飛出) (のうめん とびで)(さんこうとびで) | 室町 | 1面 | 西庄境町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 能面 鷹 (のうめん たか) | 室町 | 1面 | 朽飯町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 獅子頭 (もくぞう ししがしら) | 室町 | 1面 | 大滝町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 十一面観音菩薩坐像 (もくぞう じゅういちめんかんのんぼさつざぞう) | 平安前期 | 1躯 | 大滝町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 狛犬 (もくぞう こまいぬ) | 鎌倉 | 1対 | 大滝町 | 昭和62年9月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 狛犬 (もくぞう こまいぬ) | 室町 | 1対 | 朽飯町 | 昭和62年9月12日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来坐像 (もくぞう あみだにょらいりゅうぞう) | 平安末期 | 1躯 | 岩内町 | 昭和62年11月2日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 十一面観音菩薩立像 (もくぞう じゅういちめんかんのんりゅうぞう) | 平安末期 | 1躯 | 岩内町 | 昭和62年11月2日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 聖観音菩薩立像 (もくぞう しょうかんのんぼさつりゅうぞう) | 平安末期 | 1躯 | 檜尾谷町 | 昭和62年11月2日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来坐像 (もくぞう あみだにょらいざぞう) | 平安末期 | 1躯 | 京町二丁目 | 平成元年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 地蔵菩薩立像 (もくぞう じぞうぼさつりゅうぞう) | 鎌倉 | 1躯 | 府中三丁目 | 平成2年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 毘沙門天立像 (もくぞう びしゃもんてんりゅうぞう) | 鎌倉初期 | 1躯 | 府中三丁目 | 平成2年11月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 聖観音菩薩立像 (もくぞう しょうかんのんぼさつりゅうぞう) | 平安末期 | 1躯 | 粟田部町 | 平成3年9月 5日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 達磨大師坐像 木造 大権修利菩薩倚像 (もくぞう だるまだいしざぞう もくぞう だいごんしゅりぼさついぞう) |
江戸初期 | 2躯 | 深草一丁目 | 平成5年1月 20日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来坐像 (もくぞうあみだにょらいざぞう) | 平安後期 | 1躯 | 朽飯町 | 平成6年6月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 十一面観音菩薩立像 (もくぞう じゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう) | 平安後期 | 1躯 | 朽飯町 | 平成6年6月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 地蔵菩薩立像 (もくぞう じぞうぼさつりゅうぞう) | 平安後期 | 1躯 | 東庄境町 | 平成6年6月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 地蔵菩薩立像 (もくぞう じぞうぼさつりゅうぞう) | 平安後期 | 1躯 | 東庄境町 | 平成6年6月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 地蔵菩薩立像 (もくぞう じぞうぼさつりゅうぞう) | 平安後期 | 1躯 | 粟田部町 | 平成6年6月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 地蔵菩薩立像 (もくぞう じぞうぼさつりゅうぞう) | 平安後期 | 1躯 | 室谷町 | 平成6年6月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来立像 (もくぞう あみだにょらいりゅうぞう) | 平安後期 | 1躯 | 杉尾町 | 平成6年6月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 地蔵菩薩坐像 (もくぞう じぞうぼさつざぞう) | 南北朝 | 1躯 | 大滝町 | 平成6年6月 1日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来坐像 (もくぞう あみだにょらいざぞう) | 鎌倉 | 1躯 | 武生柳町 | 平成7年 2月 7日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 薬師如来坐像 (もくぞう やくしにょらいざぞう) | 平安後期 | 1躯 | 京町一丁目 | 平成10年2月23日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来立像 (もくぞう あみだにょらいりゅうぞう) | 鎌倉 | 1躯 | 本町 | 平成19年4月16日 |
| 市 | 彫刻 | 石造 狛犬 (せきぞう こまいぬ) | 室町 | 1躯 | 中津原町 | 平成25年1月25日 |
| 市 | 彫刻 | 銅造 如意輪観音坐像 (どうぞう にょいりんかんのんざぞう) | 鎌倉 | 1躯 | 住吉町 | 平成26年10月3日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 如意輪観音坐像 (もくぞう にょいりんかんのんざぞう) | 南北朝 | 1躯 | 文室町 | 平成26年10月3日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来立像 (もくぞう あみだにょらいりゅうぞう) | 鎌倉 | 1躯 | あおば町 | 平成27年5月8日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 菩薩立像 (もくぞう ぼさつ) | 鎌倉 |
1躯 |
御幸町 | 平成27年5月8日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来立像 (もくぞう あみだにょらいりゅうぞう) | 鎌倉 |
1躯 |
京町二丁目 | 平成30年3月6日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 不動明王立像(もくぞう ふどうみょうおうりゅうぞう) 木造 不動明王及二童子立像(もくぞう ふどうみょうおうおよびにどうじりゅうぞう) |
室町 江戸 |
1躯 3躯 |
南三丁目 | 令和2年3月16日 |
| 市 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来立像(もくぞう あみだにょらいりゅうぞう) | 鎌倉 | 1躯 | 中新庄町 | 令和4年4月11日 |
工芸 23件
| 指定区別 | 種別 | 名 称 | 時代 | 数量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 工芸 | 金銀鍍菊花文散銅水瓶 (きんぎんときんきっかもんちらしどうすいびょう) | 鎌倉 | 1口 | 武生公会堂記念館 | 平成31年10月31日 |
| 県 | 工芸 | 刀無銘(左文字) 附 打刀拵 (かたなむめい)(さもじ) (つけたり うちかたなこしらえ) | 南北朝 | 1口 | 武生公会堂記念館 | 昭和60年 4月 1 日 |
| 県 | 工芸 | 伝本多富正奉納鞍(葡萄文蒔絵鞍1背・巴散文螺鈿鞍1背・張良図蒔絵鞍1背)(でんほんだとみまさほうのうくら)(ぶどうもんまきえくら1せ・ともえちらしもんらでんくら1せ・ちょうりょうずまきえくら1せ) | 桃山から江戸初期 | 3背 | 国兼町 | 平成 3年 9月10日 |
| 県 | 工芸 | 梵鐘 (ぼんしょう) | 南北朝 | 1口 | 国兼町 | 平成27年3月31日 |
| 県 | 工芸 | 黒漆塗八角神輿 (くろうるしぬりはちかくみこし) | 1基 | 朽飯町 | 平成28年3月25日 | |
| 県 | 工芸 | 銅孔雀文磬 (どうくじゃくもんけい) | 鎌倉 | 1面 | 京町二丁目 | 平成29年3月31 |
| 県 | 工芸 | 日供膳 (にっくぜん) | 室町 | 1膳 | 大虫町 | 令和2年8月4日 |
| 市 | 工芸 | 鰐口 (わにぐち) | 室町 | 1口 | 武生公会堂記念館 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 工芸 | 竹梅文真形釜 (ちくばいもんしんなりがま) | 桃山 | 1口 | 五分市町 | 昭和47年11月 1日 |
| 市 | 工芸 | 刀 銘 国安 (かたな めい くにやす) | 南北朝 | 1口 | 武生公会堂記念館 | 昭和48年11月 1日 |
| 市 | 工芸 | 太刀 銘 有国 (たち めい ありくに) | 江戸初期 | 3口 | 中平吹町 | 昭和48年11月 1日 |
| 市 | 工芸 | 押出阿弥陀三尊及び比丘形像 (おしだしあみださんぞんおよびびくがたぞう) | 白鳳 | 1面 | 京町二丁目 | 昭和50年11月 1日 |
| 市 | 工芸 | 刀 銘 備中長船康光 (かたな めい びっちゅうおさふねやすみつ) | 室町 | 1口 | 大滝町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 工芸 | 刀拵 大刀 銘 下総大掾藤原兼正 小刀 無銘 (かたなこしらえ たち めい しもうさだいじょうふじわらかねまさ しょうとう むめい) | 時代不詳 | 2口 | 大滝町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 工芸 | 刀 銘 武蔵守藤原兼中 (かたな めい むさしのかみふじわらかねなか) | 江戸 | 1口 | 大滝町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 工芸 | 湯立釜 (ゆたてがま) | 江戸 | 2口 | 大滝町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 工芸 | 霰文真形釜 (あられもんしんなりがま) | 室町末期 | 1口 | 八石町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 工芸 | 銅孔雀文馨 (どうくじゃくもんけい) | 南北朝 | 1面 | 住吉町 | 平成26年10月3日 |
| 市 | 工芸 | 黒漆厨子 (こくしつずし) | 南北朝 | 1基 | 御幸町 | 平成27年5月8日 |
| 市 | 工芸 | 車長持 承応二年銘 (くるまながもち じょうおうにねんめい) | 承応2年(1653年) | 1台 | 深草二丁目 | 平成28年4月11日 |
| 市 | 工芸 | 車箪笥 文政二年銘 (くるまだんす ぶんせいにねんめい) |
文政2年 |
1台 | 岩本町 | 平成30年3月6日 |
| 市 | 工芸 | 金銅金幣(こんどうきんぺい) | 延宝元年(1673年) | 1串 | 大滝町 | 令和2年2月14日 |
| 市 | 工芸 | 銅鰐口 永正九年銘 (どうわにぐち えいしょうきゅうねんめい) | 永正9年(1512年) | 1口 | 広瀬町 | 令和3年3月11日 |
| 市 | 工芸 | 帳箪笥 文化四年、五年銘(ちょうだんす ぶんかよねん、ごねんめい) | 文化4年、5年(1808年) | 1基 | 武生公会堂記念館 | 令和4年4月11日 |
| 市 | 工芸 | 経机 慶安五年銘(きょうづくえ けいあんごねんめい) | 慶安5年(1652年) | 2脚 | 住吉町 | 令和4年4月1日 |
| 市 | 工芸 | 黒漆六角箱及び内容品(くろうるしろっかくばこおよびないようひん) | 室町~江戸時代 | 一括 | 京町 | 令和5年11月16日 |
書跡・典籍 9件
| 指定区別 | 種 別 | 名 称 | 時 代 | 数 量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 書跡・典籍 | 往生要集(写本)(おうじょうようしゅう)(しゃほん) | 鎌倉初期 | 9巻 | 京町三丁目 | 昭和28年 3月19日 |
| 県 | 書跡・典籍 | 版本 大般若経 (はんぽん だいはんにゃきょう) | 南北朝 | 600帖 | 朽飯町 | 昭和63年3月18日 |
| 県 | 書籍・典籍 |
大般若経568帖 (だいはんにゃきょう) |
鎌倉時代 | 586帖 | 二階堂町 | 平成29年3月31日 |
| 市 | 書跡・典籍 | 紙本墨書 真盛消息 (しほんぼくしょ しんせいしょうそく) | 室町 | 1巻 | 京町三丁目 | 昭和46年11月 1日 |
| 市 | 書跡・典籍 | 紙本墨書 実如消息 (しほんぼくしょ じつにょしょうそく) | 室町 | 1巻 | 本町 | 昭和46年11月 1日 |
| 市 | 書跡・典籍 | 少林寺文書 (しょうりんじもんじょ) | 室町 | 7点 | 中津原町 | 昭和47年11月 1日 |
| 市 | 書跡・典籍 | 徳川秀忠黒印状 (とくがわひでただこくいんじょう) | 江戸初期 | 1通 | 市武生公会堂記念館 | 昭和49年11月 1日 |
| 市 | 書跡・典籍 | 徳川家康黒印状 (とくがわいえやすこくいんじょう) | 江戸初期 | 1通 | 市武生公会堂記念館 | 昭和49年11月 1日 |
| 市 | 書籍・典籍 | 紺紙金字阿弥陀経 (こんしきんじあみだきょう) | 平安 | 1巻 | 京町二丁目 | 平成21年12月25日 |
考古資料 13件
| 指定区別 | 種別 | 名 称 | 時代 | 数量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 考古 | 松明山2号墳出土遺物 (たいまつやまにごうふんしゅつどいぶつ) | 古墳前期 | 1括 | 定友町 | 昭和63年3月18日 |
| 県 | 考古 | 石剣 (せっけん) | 弥生中期 | 1口 | 八石町 | 平成 2年5月8日 |
| 県 | 考古 | 王子保窯跡群出土鴟尾 (おおしおかまあとぐんしゅつどしび) | 7世紀後半(飛鳥時代) | 3個 | 市武生公会堂記念館 | 平成23年3月 25日 |
| 市 | 考古 | 光明山経塚出土品 (こうみょうさんきょうづかしゅつどひん) | 平安 | 5点 | 市公会堂記念館 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 考古 | 野々宮廃寺出土塼仏片 (ののみやはいじしゅつどせんぶつへん) | 奈良 | 1個 | 余川町 万葉館 | 昭和46年11月 1 日 |
| 市 | 考古 | 松明山3号墳出土品 一括 (たいまつやま3ごうふんしゅつどひん いっかつ) | 古墳前期 | 4点 | 定友町 | 昭和56年10月2日 |
| 市 | 考古 | 開山塔・五輪塔板碑 (かいざんとう・ごりんとういたび) | 鎌倉末期から室町初期 | 5基 | 荒谷町 | 昭和57年11月 1日 |
| 市 | 考古 |
弥生式土器 壷・甕 (やよいしきどき つぼ・かめ) |
弥生中期 | 各1口 | 八石町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 考古 | 陣ノ6号墳出土品 一括 (じんの6ごうふんしゅつどひん いっかつ) | 古墳後期 | 16点 | 朽飯町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 考古 | 朽飯経塚出土品 一括 (くだしきょうづかしゅつどひん いっかつ) | 室町 | 3点 | 朽飯町 | 昭和61年8月12日 |
| 市 | 考古 | 小丸城跡出土瓦 一括 (こまるじょうあとしゅつどかわら いっかつ) | 室町末 | 17個 | 万葉館、味真野小、越前市教委 | 平成 8年12月 2 日 |
| 市 | 考古 |
家久遺跡中世墓出土品 一括 附 2件(太刀・短刀片一括及び漆製品塗膜片一括) |
鎌倉初期 | 15件 | 武生公会堂記念館 | 平成 8年12月 2 日 |
| 市 | 考古 | 家久遺跡中世墓礫槨 附 礫槨の礫一括(いえひさいせきちゅうせいれきかくぼ) | 鎌倉初期 | 中世墓礫槨1基 | 越前市教育委員会 | 平成 8年12月 2 日 |
歴史資料 11件
| 指定区別 | 種 別 | 名 称 | 時 代 | 数量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 歴史資料 | 正徳元年府中図 (しょうとくがんねんふちゅうず) | 江戸(正徳元年) | 1枚 | 元町 | 昭和44年11月 1日 |
| 市 | 歴史資料 | 天保救荒碑 (てんぽうきゅうこうひ) | 江戸末期(天保8年) | 1基 | 本保町 | 昭和45年11月 1日 |
| 市 | 歴史資料 | 大塩八幡宮奉納絵馬 (おおしおはちまんぐうほうのうくら) | 江戸 | 10面 | 国兼町 | 昭和50年11月 1日 |
| 市 | 歴史資料 | 吉野神社奉納絵馬 (よしのじんじゃほうのうくら) | 江戸 | 7面 | 本保町 | 昭和53年11月 1日 |
| 市 | 歴史資料 | 向新保町の護岸築堤関係資料 (むかいしんぼのごがんちくていかんけいしりょう) | 江戸末期 | 向新保町 | 昭和54年11月 1日 | |
| 市 | 歴史資料 | 打刃物関係文書・木版 (うちはものかんけいもんじょ・もくはん) | 江戸末から明治 | 19点 | 越前市中央図書館 | 昭和57年11月 1日 |
| 市 | 歴史資料 | 本多家・佐久間家文書及び什器 (ほんだけ・さくまけもんじょおよびじゅうき) | 江戸 | 200点 | 越前市中央図書館 | 昭和60年11月 1日 |
| 市 | 歴史資料 | 石造 鬼瓦 (せきぞう おにがわら) | 江戸 | 3点 | 大滝町 | 昭和61年 8月12日 |
| 市 | 歴史資料 | 立教館及び進脩小学校関係資料 (りっきょうかんおよびしんしゅうしょうがっこうかんけいしりょう) | 江戸末から明治 | 4点 |
武生東小学校 |
昭和61年11月 1日 |
| 市 | 歴史資料 | 府中馬借街道 制札及び関係文書・記録 (ふちゅうばしゃくかいどう せいさつおよびかんけいもんじょ・きろく) | 江戸初期から後期 | 制札2点、 関係文書20通、記録1冊 |
湯谷町 | 平成29年5月11日 |
| 市 | 歴史資料 | 陽願寺皇室関係資料(ようがんじこうしつかんけいしりょう) | 江戸時代 | 4点 | 本町 | 令和3年3月11日 |
無形文化財 4件
| 指定区別 | 種 別 | 名 称 | 時 代 | 数 量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 無形文化財 | 越前奉書 (かんけいほうしょ) | 大滝町 | 平成12年6月6日 | ||
| 国 | 無形文化財 | 越前鳥の子紙 (えちぜんとりのこし) | 新在家町 | 平成29年10月2日 | ||
| 県 | 無形文化財 | 越前和紙・打雲・飛雲・水玉の製法 (えちぜんわし・うちくも・とびくも・みずたまのせいほう) | 大滝町 | 昭和50年6月3日 | ||
| 県 | 無形文化財 | 工芸技術 墨流し (こうげいぎじゅつ すみながし) | 大滝町 | 平成12年3月21日 |
有形民俗文化財 2件
| 指定区別 | 種別 | 名 称 | 時代 | 数量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 有形民俗文化財 | 越前和紙の製作用具及び製品 (えちぜんわしのせいさくようぐおよびせいひん) |
2,523点 | 越前市 | 平成26年3月10日 | |
| 県 | 有形民俗文化財 | 鶴亀松竹の算額 (つるかめしょうちくのさんがく) | 江戸(元禄14年) | 1面 | 国兼町 | 昭和57年 4月 23日 |
無形民俗文化財 9件
| 指定区別 | 種別 | 名 称 | 時代 | 数量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 無形民俗文化財 | 越前万歳 (えちぜんまんざい) | 味真野町 | 平成 7年12月26日 | ||
| 国選択 | 無形民俗文化財 | 粟田部の蓬莱祀 (あわたべのおらいし) | 粟田部町 | 平成17年2月21日 | ||
| 県 | 無形民俗文化財 | 花笠踊 (はながさおどり) | 柳元町 | 昭和55年3月11日 | ||
| 県 | 無形民俗文化財 | 大瀧神社・岡太神社の春祭り (おおたきじんじゃ・おかもとじんじゃのはるまつり) | 大滝町 | 平成14年4月23日 | ||
| 市 | 無形民俗文化財 | 日野神社の古代神楽 (ひのじんじゃのこだいかぐら) | 日野神社 | 昭和46年11月 1日 | ||
| 市 | 無形民俗文化財 | 太田新保の七夕行事 (おおたしんぼのたなばたぎょうじ) | 新保町 | 昭和46年11月 1日 | ||
| 市 | 無形民俗文化財 | 大屋町の宮座 (おおやちょうのみやざ) | 大屋町 | 昭和59月11月 1日 | ||
| 市(国選択と重複) | 無形民俗文化財 |
粟田部のお萊祀 (あわたべのおらいし) |
粟田部町 |
平成16年7月28日 |
||
| 市 | 無形民俗文化財 | 堂の餅 附 関連資料18点 (どうのもち つけたり かんれんしりょう18てん) | 粟田部町 | 平成28年8月8日 |
史跡 8件
| 指定区別 | 種別 | 名 称 | 時 代 | 数量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 史跡 | 茶臼山古墳群 (ちゃうすやまこふんぐん) | 古墳時代中後期 | 沢・岡本・広瀬・千福町 | 昭和28年 3月 19日 | |
| 県 | 史跡 | 小丸城跡 (附 野々宮廃寺跡) (こまるじょうあと)(つけたり ののみやはいじあと) | 安土桃山(白鳳) | 五分市町 | 昭和31年 3月 12日 | |
| 県 | 史跡 | 大虫廃寺塔跡 (おおむしはいじとうあと) | 白鳳 | 大虫本町 | 昭和42年 2月3日 | |
| 市 | 史跡 | 龍門寺城跡 (りゅうもんじじょうあと) | 室町 | 本町 | 昭和45年11月 1日 | |
| 市 | 史跡 | 新善光寺城跡 (しんぜんこうじじょうあと) | 南北朝 | 京町二丁目 | 昭和45年11月 1日 | |
| 市 | 史跡 | 穴地蔵古墳 (あなじぞうこふん) | 古墳時代後期及び室町時代 | 1基 | 大屋町 | 昭和46年11月 1日 |
| 市 | 史跡 | 鞍谷御所跡 (くらたにごしょあと) | 室町 | 池泉町 | 昭和47年11月 1日 | |
| 市 | 史跡 | 府中馬借街道 (ふちゅうばしゃくかいどう) | 広瀬・下中津原・湯谷・中山町 | 昭和56年11月 1日 |
名勝 3件
| 指定区別 | 種別 | 名 称 | 時代 | 数量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 名勝 | 城福寺庭園 (じょうふくじていえん) | 江戸中期 | 五分市町 | 昭和52年 2月 2日 | |
| 国 | 名勝 | 三田村氏庭園 (みたむらしていえん) | 江戸中期 | 大滝町 | 平成27年3月 | |
| 県 | 名勝 | 時水 (ときみず) | 蓑脇町 | 平成4年5月1日 |
天然記念物 16件
| 指定区別 | 種別 | 名 称 | 時代 | 数量 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 天然記念物 | 大滝神社の大スギ (おおたきじんじゃのおおすぎ) | 1本 | 大滝町 | 昭和39年6月5日 | |
| 県 | 天然記念物 | 大滝神社のゼンマイ桜 (おおたきじんじゃのぜんまいざくら) | 1本 | 大滝町 | 昭和39年6月5日 | |
| 県 | 天然記念物 | 粟田部の薄墨サクラ (あわたべのうすずみさくら) | 1本 | 粟田部町 | 昭和45年5月8日 | |
| 県 | 天然記念物 | 明光寺のオオイチョウ (みょうぎょうじのおおいちょう) | 1本 | 西庄境町 | 昭和45年5月8日 | |
| 県 | 天然記念物 | 杉尾のオオスギ (すぎおのおおすぎ) | 1本 | 杉尾町 | 昭和45年5月8日 | |
| 県 | 天然記念物 | 白山神社のバラ大杉 (はくさんじんじゃのばらおおすぎ) | 1本 | 中居町 | 昭和59年 3月 2日 | |
| 県 | 天然記念物 | 大滝神社奥の院社叢 | 大滝町 | 昭和61年3月28日 | ||
| 市 | 天然記念物 | 城福寺のヒイラギ | 1本 | 五分市町 | 昭和44年11月 1日 | |
| 市 | 天然記念物 | 白山神社のサカキ | 2本 | 大屋町 | 昭和47年11月 1日 | |
| 市 | 天然記念物 | 宗生寺のラカンマキ | 1本 | 新保町 | 昭和48年11月 1日 | |
| 市 | 天然記念物 | 味真野のサクラ | 1本 | 池泉町 | 昭和53年11月 1日 | |
| 市 | 天然記念物 | 酒列神社のアカガシ | 1本 | 米口町 | 昭和54年11月 1日 | |
| 市 | 天然記念物 | 松ケ嶽神社の大モミ | 1本 | 柳元町 | 昭和56年10月2日 | |
| 市 | 天然記念物 | 敬覚寺のイチョウ | 1本 | 下黒川町 | 昭和56年11月 1日 | |
| 市 | 天然記念物 | 横根寺のコブシ | 1本 | 横根町 | 平成元年11月 1日 | |
| 市 | 天然記念物 | 池泉のエドヒガン | 1本 | 池泉町 | 令和2年2月14日 |
国登録有形文化財 60件
| 名 称 | 所在地 | 建設年代 | 特 徴 等 | 登録基準 | 登録日 | 員数 | 構造・形式及び大きさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丈生幼稚園 (旧福井県警察部庁舎) | 京町三丁目 | 明治32年頃 | 塔屋を持つ擬洋風建築 大正13年現在地に移築 | 二 | 平成11年7月8日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺 建築面積231平方メートル |
| 井上歯科医院 | 京町三丁目 | 明治41年 | 明治36年大火後につくられた土蔵造の洋風建築 | 三 | 平成11年7月8日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺 建築面積62平方メートル |
| M工房 (旧武生郵便局) | 蓬莱町 | 大正3年 | 下見板張りの洋風建築 | 二 | 平成12年10月18日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺 建築面積99平方メートル |
| 大虫神社の宮橋 | 大虫町 | 大正7年 | 神社参道に架かる江戸切石材を用いた単アーチ橋 | 一 | 平成13年10月12日 | 1基 | 石造アーチ橋 |
| 南越 (旧中村商店) | 逢莱町 |
明治45年 昭和5年頃・昭和15年増改築 |
和風を基調としながら近代的な様相をも併せ持つ商店建築 | 二 | 平成15年7月1日 | 1棟 | 木造3階建、瓦葺、建築面積89平方メートル |
| 武生公会堂記念館(旧武生公会堂) | 逢莱町 | 昭和4年 | 南側及び東側が接道する敷地に南面して立つ。鉄筋コンクリート造地上2階建地下1階建で、南東部に6層の塔屋を配す。武生では初期の本格的鉄筋コンクリート造で、塔屋のランドマーク性を強調する垂直線意匠や、楕円等を用いた1階玄関の意匠に特徴がある。 | 一 | 平成17年2月9日 | 1棟 | 鉄筋コンクリート造地上2階一部4階地下1階建、建築面積601平方メートル 、塔屋付 |
|
越前和紙の里 卯立の工芸館 (旧西野家住宅店舗兼主屋) |
新在家町 | 寛延元(1748)年 平成7.8年移築 | 妻入の民家の前後に卯立を上げた独特の形態を持つ建物。 | 二 | 平成20年7月23日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積244平方メートル |
| 小泉家住宅主屋根 | 二階堂町 | 江戸後期 | 入母屋造妻入茅葺の上屋に、両側面後寄りと背面に切妻造桟瓦葺屋根を付け、周囲に桟瓦葺の下屋をまわし、複雑な外観をつくる。 | 一 |
平成21年11月2日 |
1棟 | 木造2階建、茅葺、建築面積350平方メートル |
| 聖徳太子堂 | 平和町58 |
嘉永元年(1848年) 明治16年改修 |
正面一間側面二間、正・側面に組高欄付の切目縁をまわし、正面に一間向拝、背面に仏壇を付設。宝形造桟瓦葺で、笏谷石の相輪を飾る。円柱で三斗組、一軒半繁垂木。内部は一室とし、格天井を張る。地域で護持される堂の一例。 | 一 | 平成23年1月26日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積18平方メートル |
| 旧根岸家住宅主屋 | 岩本町16字中町8-1 |
明治前期 大正7年改修 |
正面16メートル、奥行18メートル 、切妻造妻入桟瓦葺の木造二階建。前寄りに土間、奥に床上部を設け、最奥にトコや仏壇を構える。正・背面に大きなウダツをたてるなど、地域的な特色が顕著な民家である。 | 二 | 平成23年1月26日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、建築面積229平方メートル |
| 旧根岸家住宅土蔵 | 岩本町16字中町8-1 | 昭和前期 | 桁行12メートル 、梁間5.9メートル と規模の大きい二階建土蔵。切妻造桟瓦葺。西面は全面に庇を付け、腰モルタルの漆喰仕上げ。その他は高く下見板を張る。内部は一、二階とも南北二室に分け、真壁で柱や貫を現す。 | 一 |
平成23年1月 26日 |
1棟 | 土蔵造2階建、瓦葺、建築面積90平方メートル |
| 旧根岸家住宅表門 | 岩本町16字中町8-1 | 昭和前期 | 水路に架かる橋を介して通りに面する。間口3.9メートル 、切妻造桟瓦葺で、北側に便所を付設。両端に方柱をたて、差物で固め、腕木を前後に出し、軒桁をもち出し、一軒疎垂木の軒を支持。北半部を板壁とし、板戸を引き込む。屋敷正面を画する簡易な門。 | 一 | 平成23年1月26日 | 1棟 | 木造、瓦葺、間口3.9メートル 、便所付 |
| 旧大井百貨店(大井洋装店) | 元町81他 | 昭和5年頃 | 間口8.7メートル 、奥行28メートル 、鉄筋コンクリート造三階建で地階をつける。正面入口上部に装飾的な半円アーチを設け、街路に面する北及び西面に大オーダーを廻らし、柱間に3連窓を配する。当地の賑わいを物語る近代商業建築。 | 一 | 平成25年12月24日 | 1棟 |
鉄筋コンクリート造3階建地階付、建築面積239平方メートル |
| 福井鉄道北府駅本屋 | 北府2-3字東土井田20-2 |
大正13年 平成24年改修 |
桁行14メートル 、切妻造、妻入の木造平屋建で、西側に1間幅の下屋を張出す。待合室入口及び改札口の小壁に横長窓を穿ち、待合室脇の旧売店の出窓をショーウインドー風につくるなど特徴的な外観をもつ地方鉄道の駅舎。 | 一 | 平成25年12月24日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺一部鋼板葺、建築面積101平方メートル |
| 寿屋対碧亭 | 粟田部町29字船佐山41 | 昭和6年頃 | 木造平屋建、入母屋造茅葺で、南西隅に桟瓦葺の四畳半を張出す。主体部はトコ付の六畳の西側に四畳前室を、東側に山形窓のトコをもつ二畳を配し、周囲に下屋を廻らせる。四畳半には円窓など多彩な窓を穿つ、開放的な構成の草庵風茶室。 | 一 | 平成25年12月24日 | 1棟 | 木造平屋建、茅葺一部瓦葺及び銅板葺、建築面積60平方メートル |
| 福井鉄道北府駅車両工場 | 北府2-5字中藤牧6-1 | 大正末期 | 北府駅構内に建つ建物で、桁行22メートル 、梁間13メートル 、切妻造、外壁下見板貼とし、福井鉄道の前身の福武電気鉄道時代から稼働する建物。 | 一 | 平成27年11月17日 | 1棟 | 木造平屋建、金属板葺、建築面積298平方メートル |
| 福井鉄道バス旧車庫 | 北府2-5中藤牧3-2 | 大正8年 昭和31年改築 | 車両工場に隣接して建ち、桁行27メートル 、梁間15メートル 、切妻造の東西に長い建物。両妻面にはバスが出入りする10メートル の開口部が設けられている。旧今立町の岡本小学校講堂を改築改造した建物。 | 一 | 平成27年11月17日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積396平方メートル |
| 愛山荘 主屋 | 若竹町14字天野1-4 | 大正5年 | 1階は玄関奥に前室を介して座敷2室を並べ、庭園に向けて畳縁を廻らす開放的な造り。2階は日野山を望む東西に板縁を設け、銘木を用いた座敷廻など近代的な趣向が凝らされた建物。 | 二 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、建築面積244.7平方メートル |
| 愛山荘 離れ | 若竹町14字天野1-4 | 大正5年 昭和17年増築 | 6畳の「旧離れ」と10畳と6畳からなる「離れ」からなり、端正な造りで、床廻りに円窓を配するなど、近代的な意匠を持つ建物。 | 二 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積151.3平方メートル |
| 愛山荘 蔵座敷 | 若竹町14字天野1-4 | 昭和3年 | 主屋に南西に渡り廊下で接続する建物。北面下屋に玄関を設け、外壁はモルタル洗出仕上げに目地を入れ、渦の模様の鋼製持送りで庇を設ける。内部は1階を檜を用いた上質な座敷とする。 | 一 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、建築面積50.7平方メートル |
| 愛山荘 一の蔵 | 若竹町14字天野1-4 |
大正5年頃
|
妻入建物で東面に蔵前を付す。内部は欅を用いた堅牢な造り。軒裏まで漆喰塗と腰板壁の外壁が街路景観を創造している。 | 一 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、47.3平方メートル |
| 愛山荘 二の蔵 | 若竹町14字天野1-4 | 大正5年頃 |
平入の建物で東面に蔵前を設ける。正面では、両開扉を5段の掛子塗とし、腰部なども黒漆喰仕上げとし、重厚な外観を見せる建物。 |
一 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、建築面積73.7平方メートル |
| 愛山荘 石蔵 | 若竹町14字天野1-4 | 昭和11年 | 平入の建物で笏谷石を積み扉口や窓は鉄扉ととし、内部はモルタル仕上げである。小屋組は中央に鉄製のトラス梁を入れ棟木を受けるような特徴的な外観見せる建物。 | 一 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、建築面積88.5平方メートル |
| 愛山荘 茶室 | 若竹町14字天野1-4 | 昭和3年頃 昭和後期 | 良材を使った瀟洒な造りで、節付の丸太材や皮付きの赤松や竹を用いて野趣も加味している。蔵座敷と一帯となり、端正な中にも変化に富んだ意匠を見せる建物。 | 二 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積32.8平方メートル |
| 愛山荘 待合 | 若竹町14字天野1-4 | 昭和3年頃 昭和後期 | 主に丸太が用いられ、袖壁には下地窓が用いられるなど、数寄屋風意匠を見せ、露地空間を良好に形成している。 | 一 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造平屋建、金属板葺、建築面積4.7平方メートル |
| 愛山荘 門及び塀 | 若竹町14字天野1-4 | 大正5年頃 | 敷地西面を画す門と塀。門は腕木門で引分けの板戸と格子戸を建て込む。塀は真壁で外側は板張りで内側は杉皮張りとし、景観を整えている。 | 一 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺 |
|
西野家住宅 主屋 |
定友町4字福岡8-1 | 江戸末期 大正前期移築 平成2年改修 | 池田町の農家を移築した建物で、大正期に背面へ増築している。東妻面に卯建を立ち上げ、当地方特有の外観を見せる。 | 二 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、金属板葺、建築面積221.2平方メートル |
| 西野家住宅 離れ | 定友町4字福岡8-1 | 昭和12年 | 主屋の背後に接続する建物で、床構えは銘木を用いたり、彫刻欄間に優れた技術が施されている建物。 | 二 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積87.1平方メートル |
| 西野家住宅 蚊帳蔵・味噌蔵・紙蔵 | 定友町4字福岡8-1 | 江戸末期 大正14年頃増築 | 東3間の蚊帳蔵と中央2間の味噌蔵は一連の切妻屋根で、西6間の紙蔵は増築で棟を一段高くする建物で、屋敷の拡充課程が良く示されている。 | 一 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造2階建(紙蔵は3階建)、瓦葺、建築面積 |
| 西野家住宅 新蔵・中蔵・大蔵 | 定友町4字福岡8-1 | 明治23年頃 昭和前期増築、平成5年改修 | 北4間の大蔵と南5間の新蔵を1間半の中蔵で繋ぐ。東面全面に下屋を設ける。大蔵の扉口は、土戸・板戸・格子戸を吊る重厚な造りで、新蔵、中蔵ともに黒漆喰を用いて正面を飾っている。 | 一 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造2階建、金属板葺、建築面積154.4平方メートル |
| 西野家住宅 茶室 | 定友町4字福岡8-1 | 明治42年頃 | 切妻造で6畳と4畳半を南北に並べ、南西に矩折れに廊下を巡らす。外壁は漆喰塗で腰板壁をし、内部は軸部に透漆、天井廻縁や棹縁に黒漆を施すが、床柱と落掛は素木のままとする。 | 一 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積81.9平方メートル |
| 西野家住宅 塀 | 定友町4字福岡8-1 | 昭和12年 昭和前期増築 | 敷地北面を画す塀で、東半は笏谷石の切石積、西半は亀甲積と異なる石垣上に建ち、柱上は肘木上の腕木で出桁を受け、桟瓦葺の屋根を架ける。 | 一 | 平成29年6月28日 | 1棟 | 木造瓦葺 |
| 陽願寺本堂 | 福井県越前市本町154 | 明治35年 | 境内中央に東面して建つ寄棟造の大型本堂。外陣には広縁と落縁を廻らすが、両側面の広縁奥寄りを堂内化して外陣を拡張する。内外陣堺は金箔と彩色で飾る。北余間に鞘の間を取り込んで御簾の間とするなど、高い寺格を示す。 | 二 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積617平方メートル |
| 陽願寺庫裏 | 福井県越前市本町154 |
明治前期 昭和39年代増築 |
本堂北に建つ切妻造の東西棟で、東正面の妻壁を大虹梁と海老虹梁で飾る。東の玄関は上部に重厚な小屋組を現す。北の台所は土間に床板を張り、中央の板敷は小屋裏を居室とする。南の式台玄関を対面所から移築するなど、一部改造があるが近世以来の様相を示す。 | 一 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積292平方メートル |
| 陽願寺対面所 | 福井県越前市本町154 | 明治前期 明治44年改修 |
庫裏の西に続く東西棟。東から広間20畳と使者の間16畳で、対面所16畳は西面に床と棚を飾る。使者の間と対面所の南は一間幅の畳敷広縁とする。欄間は竹の節である。対面所の西背後の松の間は6畳の小座敷で控の間とする。高い格式を備えた接遇施設。 | 二 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、 建築面積182平方メートル |
| 陽願寺御殿 | 福井県越前市本町154 | 明治35年頃 | 対面所の西に続く東西棟である。西の座敷と東の次の間は格10畳で、座敷の西面に大床を設け、南に畳敷の広縁を通し、落縁と土縁が付く。座敷北の御座の間は奥の6畳を上段に造り、床、棚、書院を設ける。本山門主の接遇を想定した上質な空間を実現している。 | 二 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、 建築面積169平方メートル |
| 陽願寺洋館 | 福井県越前市本町154 | 昭和9年頃 | 御殿の南面落縁から西に続く東西棟で寄棟造とする。中央の応接室は、南面を台形平面のベイウインドウとし、庭への扉口を設ける。西は書斎で両室とも漆喰塗天井に中心飾りを付す。北に片廊下を通し、御殿との間は便所とする。落ち着いた意匠の応接空間である。 | 二 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、 建築面積45平方メートル |
| 陽願寺客殿 | 福井県越前市本町154 | 昭和17年頃 | 洋館の西に接続する南北棟で二階建の入母屋造。桁行中央に階段室を設け、二階南の10畳主座敷に、床、棚、書院を設け、南に縁を付す。階段から北は上下階とも6畳2室で、二階は数寄屋風座敷、一階北室は内仏の間とする。寺院内の詩的空間の有り様を示す。 | 二 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、 建築面積71平方メートル |
| 陽願寺納骨堂 | 福井県越前市本町154 | 昭和26年 | 境内の北東隅に建つ宝形造で相輪を戴く。洗出しの基壇をもち、南正面扉口を門形の枠で飾り、両側面は出窓状に壁面を張りだし縦長窓を開く。背面下屋の仏壇両脇から基壇内の納骨室に到る。正側面の高窓から、柔らかく外光を取込むなどの造形を試みている。 | 二 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 鉄筋コンクリート造平屋建、瓦葺、 建築面積21平方メートル |
| 陽願寺土蔵 | 福井県越前市本町154 | 明治30年頃 | 境内の北西隅に建つ東西棟である。東妻に瓦葺の下屋を付し南半に戸口を設け、北半に漬物小屋を造る。外壁は白漆喰塗に簓子下見張りとし、妻壁も塗込めて母屋の形を見せる。小屋組は緩い曲がりの梁に束立で棟木と母屋を受ける。境内背後の景観を後世する土蔵。 | 一 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 土蔵造2階建、瓦葺、 建築面積51平方メートル |
| 陽願寺鐘楼 | 福井県越前市本町154 | 明治23年 | 境内東辺中央に開く山門南側の南北棟で入母屋造。反りのある切石積基壇に建ち、礎盤上に円柱を立てる。虹梁形内法貫は木鼻を獅子とする。頭貫と台輪は彫刻で飾る。組物は出組詰組で、軒は二軒扇垂木とする。禅宗様を基調とした手の込んだ造形である。 | 二 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 木造、瓦葺、 建築面積13平方メートル |
| 信洋舎製紙所漉場棟 | 福井県越前市定友町五字相生12他 | 明治後期 | 桁行約19メートル、梁間約6・5メートル、南北棟の工場建築で、内部を広い一室とする。紙を漉くための漉場として用いられる。採光通風のため、連続したガラス窓は内外の意匠を特徴付ける。 | 一 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、 建築面積133平方メートル |
| 信洋舎製紙所旧休憩場及び張場棟 | 福井県越前市定友町五字相生12他 | 明治19年 | 場棟の南、ボイラー及び旧ロール場棟の東に接続して東西棟で建つ。二階を張場とし、一階はかつて休憩場として使った。張場は張り板に張った紙を乾燥させるための場所で、乾燥機を用いた専用の乾燥部屋も持つ。二階は採光通風のためガラス窓を大きく取る。 | 一 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、 建築面積51平方メートル |
| 信洋舎製紙所ボイラー及び旧ロール場棟 | 福井県越前市定友町五字相生12他 | 明治中期 | 旧休憩場及び張場棟の西、旧塵取場及び仕上場棟の南に接続して南北棟で建つ。一階をボイラー室とし、二階を艶付けのためのロール場として使った。簡素な建物であるが、内部には明治期の艶付ロール機器も残され、製紙業の手工業からの近代化の過程を伝える。 | 一 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、 建築面積122平方メートル |
| 信洋舎製紙所旧塵取場及び仕上場棟 | 福井県越前市定友町五字相生12他 | 明治32年 | ボイラー及び旧ロール場棟の北に接続して建つ。桁行約18メートル、梁間約5・5メートルで、二階を仕上場、一階を塵取場に使った。内部は広い一室空間とし、上下階ともガラス窓を連続させて採光通風に工夫する。地場産業である製紙の最終工程を担う建物。 | 一 | 令和2年8月17日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、 建築面積101平方メートル |
| 旧浅井薬店(小澤金物店)店舗兼主屋 | 福井県越前市幸町222-1 | 昭和6年 | 武生城下の中心部に位置。二階建切妻造桟瓦葺。正面の出入り口脇にショーウィンドウを構える。内部は土間脇に旧調剤室があり板間のミセを張り出す。奥の通り土間沿いに八畳、奥に浴室便所などを突出する。表構えに当時の流行を取り入れた商店。 | 一 | 令和3年2月4日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、建築面積101平方メートル |
| 岩野平三郎製紙所事務所 | 越前市大滝町 | 明治元年/昭和中期 | 越前和紙の産地、旧今立町にある製紙所。事務所は谷間の南北に長い敷地中央北寄に南面して建つ。木造二階建、切妻造桟瓦葺で正面に下屋を付す。外壁は下見板一部竪板張で、上部は真壁造。内部一階は事務所、二階は和室を配する。敷地北半の屋敷景観を整える。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、 建築面積68平方メートル |
| 岩野平三郎製紙所主屋 | 越前市大滝町 | 明治元年/大正後期増築、昭和8年頃・同30年頃改修、同中期増築 | 事務所北西に接続し、東面して建つ。二階建切妻桟瓦葺の北棟と棟を直行させた南棟を平屋で接続し東・北面に深い下屋を付す。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 木造2階一部平屋建、瓦葺、 建築面積218平方メートル |
| 岩野平三郎製紙所土蔵及び繋ぎ屋 | 越前市大滝町 | 大正後期 | 敷地北端に南面して建つ二階建の土蔵。正面に下屋を付し、外壁は漆喰で軒先まで塗込めて腰を下見板張とする。二階東側には床付の座敷を配する。土蔵南西に伸びて主屋に接続する繋ぎ屋は内部に風呂等を備える。丁寧なつくりで、北辺の屋敷景観を引き締める。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 土蔵造2階及び木造平屋建、瓦葺、 建築面積125平方メートル |
| 岩野平三郎製紙所煮釜場 | 越前市大滝町 | 昭和27年 | 敷地中程東辺に西面して建つ原材料の繊維の煮沸、洗浄用の施設。片流れ鉄板葺の南北に長い平面で、敷地の高低なりに北半を一段低くつくる。外壁は竪板張とする。北半の二室と南半一室に区分し、南半に釜場と洗い場を設ける。和紙製造施設の沿道景観を構成。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 木造平屋建、鉄板葺、 建築面積40平方メートル |
| 岩野平三郎製紙所ビーター場 | 越前市大滝町 | 昭和28年 | 敷地南端に建つ原材料の繊維の塵取り、叩き解し用の施設。木造平屋建切妻造桟瓦葺で、南に下屋、北東に落棟の突出部を付す。外壁は下見板張で、連続した横長窓で開口を広くとる。内部はキングポストトラスの小屋組を現す大空間。一連の施設景観の南端を担う。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、 建築面積145平方メートル |
| 岩野平三郎製紙所ビーター場 | 越前市大滝町 | 大正後期/昭和28年改修 | ビーター場の北に接続して建つ紙漉き、脱水用施設。切妻造のL字型平面で、東西棟の漉き場と南北棟で東面に下屋を付した圧搾場からなる。漉き場内部は天井が高く、南東面は上下二段に窓を開いて採光を図る。狭隘な敷地なりに建つ広大な施設が存在感を放つ。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 木造平屋一部2階建、瓦葺、 建築面積407平方メートル |
| 岩野平三郎製紙所張り場及び乾燥場 | 越前市大滝町 | 昭和28年/同40年増築 | 圧搾場の北に接続し、東面して建つ。南北棟の木造二階建、切妻造桟瓦葺で、正面北寄出入口に庇を架ける。外壁は下見板一部竪板張とする。東側にトラスで大スパンをとばした大部屋の作業空間をつくり、西側に小部屋の乾燥室を配す。敷地中央の景観を形成。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、 建築面積236平方メートル |
| 岩野平三郎製紙所コグラ | 越前市大滝町 | 昭和24年 | 事務所の東方、街路に沿って南面して建つ。もと大判和紙の乾燥場。土蔵造二階建、桟瓦葺で背面に下屋を付す。外壁は漆喰で軒先まで塗込め腰をモルタル塗とする。内部は上下階とも一室で一階は土壁、二階は竪板張。煮釜場と共に敷地東辺の沿道景観を形成する。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、 建築面積41平方メートル |
| 岩野平三郎製紙所旧大工小屋 | 越前市大滝町 | 昭和31年 | コグラの北に近接し西面して建つ。もと和紙出荷用の梱包木箱の製作所と伝える。木造平屋建、切妻造桟瓦葺で、西面に下屋を架ける。外壁は下見板張で上部を土壁とする。内部は一室で土間床に竪板張の壁とし、束立の和小屋を表す。敷地中ほどの一点景をつくる。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、 建築面積34平方メートル |
| 馬場家住宅主屋 | 越前市広瀬町 | 明治24年頃/明治39年増築改修、昭和前期増築 | 越前市街地西方に位置し、敷地中央に南面する。南北棟の二階建切妻造桟瓦葺の主体部の西に角屋を伸ばして玄関とし、周囲に下屋を付す。主体部南半に台所、北半に五室を配し、庭に臨む東側に座敷を配す。束と貫を整然と重ねた妻面をみせる越前の豪壮な民家。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、 建築面積245平方メートル |
| 馬場家住宅土蔵 | 越前市広瀬町 | 明治25年 | 敷地北西隅に建つ土蔵。桁行四間半、梁間三間、二階建切妻造平入桟瓦葺の東西棟で、南面東寄りを戸口とし下屋を付す。腰高に切石積基礎を積み、外壁は漆喰塗で軒まで塗込め、下部を下見板張とする。戸口廻りは漆喰塗で柱や楣を造り出し、特に意匠を凝らす。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、 建築面積56平方メートル |
| 馬場家住宅長屋門 | 越前市広瀬町 | 文久2年(1862)/大正2年移築 | 主屋の南西に南面して建つ。桁行六間半梁間二間半の東西棟の入母屋造平入桟瓦葺の北西に桁行二間梁間二間の突出部を持ち、全体としてL字形の平面とする。南面中央二間を門口とし、両開の板戸を吊って両脇にそれぞれ潜戸を設ける。旧家の風格を示す長屋門。 | 一 | 令和3年2月26日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、 建築面積78平方メートル |
| 吉田家住宅(旧東小林家住宅)主屋 | 越前市岩本町 |
明治前期/昭和4年改修 |
越前和紙産地の岩本町に所在する在郷商家の主屋。敷地中央に西面する二階建切妻造平入桟瓦葺で、西面南を戸口とする。一階は四室で東南室で座敷棟に接続し、二階は東半を座敷とする。越前地方民家の定型に近い造りで、和紙で栄えた地域の歴史を伝える主屋。 | 一 | 令和4年10月31日 | 1棟 | 木造2階建、瓦葺、建築面積81平方メートル |
| 吉田家住宅(旧東小林家住宅)座敷棟 | 越前市岩本町 | 江戸末期/昭和10年改修 | 在郷商家の主屋の東側に接続する座敷棟。平屋建切妻造妻入桟瓦葺で、内部は西面南寄りに設けた式台から仏間を抜けて座敷に至る。座敷は東面に床の間を構え、南北二面に縁を付す。座敷は長押を廻さず、簡素ながらも柱や天井を漆塗で仕上げた華やかな座敷棟。 | 一 | 令和4年10月31日 | 1棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積59平方メートル |
登録基準
一、歴史的景観に寄与している建造物
二、造形の規範となっている建造物
三、再現することが容易でない建造物
国登録記念物 2件
| 名 称 | 所 在 地 | 説 明 | 種 別 | 登録基準 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花筐公園 | 粟田部町 |
江戸末期の桜の名所を母体として、近代から第2次世界大戦後にかけて整備された公園で、今日もなお保健・休養の場として重要な機能を持つ都市公園である |
名勝地 | 一 | 平成19年7月26日 |
| 市川鉱物研究室収蔵標本 | 中新庄町 | 市川新松コレクションは、日本の鉱物学研究の黎明期に水晶の蝕像を研究し、世界的な業績を残した市川新松が研究に使用した鉱物標本類のコレクションである | 動物、植物及び地質鉱物 | 三 | 平成24年9月19日 |
名勝地関係登録基準
一、造園文化発展に寄与しているもの
二、時代を特徴づける造形をよく遺しているもの
三、再現することが容易でないもの
動物、植物及び地質鉱物関係
一、我が国において作り出された飼養動物及び飼育地
二、我が国において作り出された栽培植物及び生育地
三、動物、植物並びに岩石、鉱物及び化石の標本
四、前三号に掲げるもの以外の地域独特の自然物又は自然現象