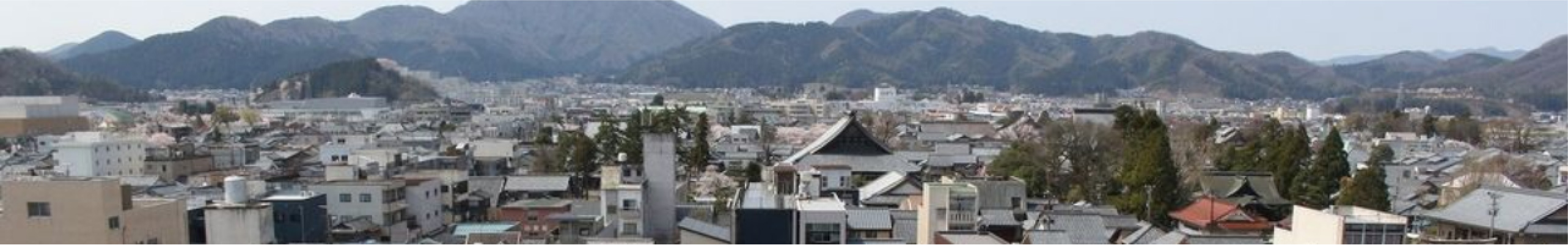最終更新日 2025年8月8日
やまけんコラム 令和6年度
PAGE-ID:12200
やまけんコラム「宝をつむぐまち」 令和6年度分
めだかの学校 VOL.25
学校の帰り、近くの服部川にかかる木の橋の上から、ウグイやフナが群れ泳ぐ様子を飽かず見ていたものだ。通学路と田んぼの間を流れる小川、「めだかの学校」は普通の光景だった。いったい、どこに行ってしまったのだろう。水が汚れ、棲み家も壊された。「絶滅危惧Ⅱ種」の一つとしてめだかが掲載されたのは、1999年のことだという。
10年ぶりに本市で全国めだかシンポジウムが開催され、「武生めだか連絡会」などの市民団体が主幹事となって、講演会、情報交換や活動報告などが行われた。本市での、コウノトリをシンボルに豊かな自然環境を守り、伝えていく、絶滅危惧種の保全やビオトープづくりなど、里地里山の保全再生活動も紹介された。
本市は、5月に化学肥料や農薬を使わない有機農業に市を挙げて取り組む「オーガニック都市宣言」を行った。有機栽培面積は325ヘクタールと昨年の276ヘクタールから大幅に拡大しており、福井県ではトップ、全国でも有数の有機農業の産地となった。有機農業は、自然環境を再生しつつ農業を存続させる一つの道だと思う。
シンポジウム会場前で展示されていた水槽の中のめだか。つい懐かしくなって5匹を分けてもらい飼いはじめた。水草を入れ、耳かきのような匙で粉の餌をやる。愛らしい姿、元気な泳ぎに癒される。
いろいろな生き物の姿は豊かな自然の象徴。そこに暮らす人間の心に潤いをあたえ、元気と長生きにもつながる。しかし、めだかの居るべき場所は、本来水槽ではなく「川の中」なのだろう。少し申し訳ない気持ちで独り眺めている。
(越前市広報R6年12月号)
紫式部の旅 VOL.24
「紫式部の旅」は、10月18日、宇治十帖や道長の子、頼道が建立した平等院のある宇治市の宇治上神社の「出立の儀」に始まった。午後には源氏物語の着想を得たとされる大津市の石山寺を詣で、さらに琵琶湖畔で、船出の儀式を再現。翌日、敦賀の氣比神宮で越前の国に入る「境(さか)迎えの儀」を行い、南越前町の「鹿蒜(かひる)神社」へ。最終日は総社大神宮から市役所までの行列と着任の儀式である。連携してプロジェクトを進めるそれぞれの市町の首長が参加して思いを語り、旅の監修をお願いした福嶋先生の軽妙かつ学識あふれる解説も大いに見学者を楽しませた。
当時は船や馬、輿、徒歩での移動で、途中宿場や寺に泊まりながら進み、延喜式の規定によると越前までは4日程要した(実際は5日という説もある)とされている。『紫式部集』の歌からルートを探ると、山城と近江の国境の逢坂関(おうさかのせき)を越え、打出浜(うちでのはま・大津市)まで陸路を行く。ここから舟で琵琶湖を北上し、塩津(長浜市)で上陸後、深坂峠(ふかさかとうげ)を越え敦賀に入る。敦賀以降は、残念ながら歌が残っていない。長旅につかれ、もはや歌を詠む余力がなかったのかもしれない。木の芽峠を越えて鹿蒜駅(南越前町)に至り、越前国府へ向かったとするが有力であるが、山中峠を越えた、あるいは海路を利用し、河野から上陸したという説もある。
藤原為時が越前国守に任命され、式部も一緒に越前へと移り住んだ千年後の1996年、紫式部越前武生来遊千年記念事業「紫式部千年祭」が開催され、下向の旅も行われた。今回は28年ぶりに、大河ドラマ「光る君へ」を機に行ったのである。
公募による参加者が華やかな小袿や狩衣(かりぎぬ)などの平安衣装をまとい、それぞれのスポットで儀式や行列を繰り広げた。最終日の為時役は本市が誇るフェンシングオリンピックメダリスト見延和靖選手が務め、凛々しい姿を見せてくれた。
最終日の越前市のパレードは、天気にも恵まれ、大勢の市民が見に来てくださった。市民の誇りにつながり、また、本市の歴史や文化が多くの人に知られるきっかけになればと願う。
式部が歩んだ道のりを追いながら、千年前の空気がよみがえるような心持がしていた。都からの行きかえり、越前国府の滞在の中で、それまでの人生で経験のなかった風景や匂い、異文化の人の暮らしぶりを肌で感じたことが、彼女の才能と感性を覚醒させた。そして『源氏物語』に広がりと深みを与えたことは間違いない。このことを確信した、時空を超える「私自身の旅」でもあった。
(越前市広報R6年11月号)
菊薫る季節 VOL.23
中国の詩人、陶淵明(とうえんめい)は、酒に菊の花を浮かべて飲めば邪気を払って息災、という重陽の節句(ちょうようのせっく)(9月9日)の日、酒がないので菊だけを食べることにするわい、とユーモアあふれる文を書いている。
菊は、その中国から8~9世紀ごろ我が国に伝わった。平安時代、菊花が延命の力を持つということから、重陽の節句の前夜から菊花に綿を置いて香りと露を染み込ませ、その朝に顔を拭いて長寿・延命を願う「菊の被綿(きせわた)」という風習があった。
『紫式部日記』には、道長の妻、倫子(ともこ)(大河ドラマでは黒木 華(くろきはる))から、その綿が贈られたお礼の和歌が記され、結局その歌は送らなかったとある。「老いを払わないといけないのはそちらの方よ」、皮肉の返しではとの、うがった解釈もあって「おもしろし」である。
73回目となる「たけふ菊人形」が開幕した。菊人形この規模で行っているところはほかにないと聞く。武生は昔から菊づくりが盛んな土地で、江戸時代には数多くの寺社で品評会が開かれ、菊作りを競い合っていた。戦後、まちに活気を取り戻したいと始めたのが「たけふ菊人形」である。栽培は難しく、とりわけ大輪の菊の栽培には高度な技術を要する。味真野の万葉菊花園では千輪菊や懸崖菊(けんがいぎく)などの伝統的な栽培技術を継承し、農家への指導も行っている。
この伝統の菊作りや菊の人形は、日本文化を象徴する外国人観光客向けのコンテンツとして魅力がある、と観光庁に認められた。しかも他では用意できない。自動走行モビリティによる体験も用意し、夜の菊人形会場のナイトツアーを企画した。改めて菊に光をあてる契機になるかもしれない。
本市には長い歴史と伝統の中で生まれ、育まれてきた職人の技、文化、芸能、祭りが存続し、市民団体によって続けられているイベントも多い。
そこには、時代の変化に応じながら継続する、根源的な力があると感じる。これこそが、宝なのだ。
(越前市広報R6年10月号)
中華そばめぐり VOL.22
今回は中華そばである。先月の「日野川のアユ」に続いて食べ物の話だが、ふるさとの記憶として味覚ほど強いものはないように思うのでご容赦願いたい。
中華そばは、おろしそばと並んで、知る人ぞ知る本市の名物の一つ。ボルガライスと合わせて三大グルメである。
戦後のインスタントラーメンブームで、「ラーメン」が普及したが、旧JR武生駅前周辺では「中華そば」という伝統の名前が使われ続けてきた。今も、市内には「中華そば」を出す食堂やそば屋が20店ほどある。自家製麺が売りのお店、越前市産のメンマを使用するお店など、それぞれに個性がある。
しかし、ラーメンの世界とは一線を画していて、透き通ったスープ、チャーシュー、青ねぎ、メンマ、そして、かまぼこやハムと、伝統が守られている。全国チェーンのラーメン店では得られない昔ながらの味を楽しむことができるのだ。
この地には豊かな農業があり、職人の手仕事による工芸品が産地を形成し、繊維産業も盛んで、先端的な企業も立地した。地元に雇用があって消費もする、地域でお金が回る経済が維持されてきた。その地域経済の基盤があったから、ごく普通だけれども、とても美味しい食堂、古いたたずまいを残す情緒ある料亭が多く続いているのだと思う。これからも、地元の食堂で食べ、料亭を使い続けることによって、ふるさとの食文化という宝物を守ることができる。
ささやかな貢献をと考え、おろしそばめぐりに加えて中華そばめぐりを始めたのだが、思い出すのは中学校の部活の帰りに食べた同級生のうちがやっていた食堂の中華そば。そのころの幸せな気分がよみがえる。
(越前市広報R6年9月号)
日野川のアユ VOL.21
国高小学校の校長室で、小林英典校長と相向かいになって給食と一緒にアユの塩焼きを食べた。学校の様子を聞きながら、校長先生が給食開始の30分前に必ず行うことになっている「検食」の時間を共にしてのことであった。
「ふるさとのアユの味を子どもたちにぜひ知ってもらいたい」という日野川漁業協同組合のみなさんの熱い思いをお聞きしたのは2年前のことである。昨年度は、「給食の基準」を満たして何とかしようと検討した結果、唐揚げで提供することになった。
ただ、アユといえば「香魚」とも呼ばれる夏の味覚。塩焼きを「頭からしっぽまで食べる」方が、育った環境やえさとなる藻によって変わるらしい内臓の味を楽しめる。というより、なんと言ってもうまいと思う。食通として知られる北大路魯山人も、はらわたの部分が一番美味まいと言っているとか。
今年は、教育委員会と農政課がさらに工夫をし、「食育」の一環として、市内の小学6年生に地元のアユを塩焼きで食べてもらうことになった。日野川漁業協同組合の組合員の方から、生態系やアユは河川の美しさを図るバロメーターであることなどを、食べる前に子どもたちに教えてもらった。アユはすべて漁協から安く提供いただいた。まさに、食育、環境教育、ふるさとを愛する心を育むふるさと教育であり、本当にありがたいことである。
日野川は、日野山と並ぶ本市の象徴、九頭竜川水系最大の支流である。「アユの川」として知られ、関西圏からも多く釣り人が訪れる。日野川漁業協同組合による稚アユ放流会が、今年は4月21日に行われ、私も親子連れ約200人と一緒に参加した。5月にかけて約80万尾が放流されたが、これは全国的にも特に多い数である。
子どもたちの中には初めて食べる子もいたようだが、頭からかぶりついて「おいしい」と、たくさんの笑顔が見られた。実際に食べて、「ふるさとの味」が、舌と心に刻まれたはずである。
子どもの頃、親に日野川の上流、今庄あたりでの友釣りに連れて行かれた。まるで釣れなくて、以来、ずっと食べる専門なのだが、アユの苦みは、懐かしい日野川の思い出の味である。
(越前市広報R6年8月号)
新紙幣発行 VOL.20
新しい紙幣が20年ぶりに、7月3日、発行された。一万円札の肖像画が、聖徳太子から福沢諭吉になってからは、早や40年も経つのだという。今回は、数年前に大河ドラマの主人公にもなった渋沢栄一に代わる。
ご存じのように越前和紙の産地、五箇地区は、「お札のふるさと」である。
現存する最古の藩札、福井藩の藩札は、越前和紙によるものである。当時、その技術は絶対秘密で、紙漉業に関係しない住民まで移住が禁止されるなど、厳重な取り締まりが行われたそうである。
そして、福井藩士であった由利公正の建議により発行された、明治政府の太政官札に越前和紙が採用された。福井藩の財政再建に活躍し、和紙業の振興や藩札の発行にも関わっていたのであった。新政府において「五箇条の御誓文」を起草しており、福井県立図書館では原案を見ることができる。
太政官札の後には、ドイツに依頼し、新紙幣(ゲルマン紙幣)が発行されたが、改めて和紙の良さが見直され、越前和紙の「7人の職人」が技術指導者として招聘されることになる。門外不出の 技術を持ち出したことから、村には戻れない悲壮な覚悟であった。
越前和紙の高い技術力は、贋札防止のためのすかし技術など、新札用紙の改造に大きな貢献を果たしたのである。和紙の神様を祀る岡太神社が、印刷局内に分祀されたのも、こうした物語があるが故であった。
今回の新紙幣では、数字を大きくするユニバーサルデザインを採用、「すかし」が肖像部分のほか背景にも細かく入り、3Dホロ グラムも採用されている。まさに、印刷局工芸官の神(紙)業の粋であるが、そこには、今も、越前和紙のすかしの技術がDNAとして生きているのである。
さて、忘れてはならないのが二千円札。本市ゆかりの紫式部と源氏物語が描かれている。発行から20年、流通量も少なく、若い人の中には、見たことがない人も多いだろう。だが、幸い現役は続くとのこと。今年の大河ドラマ「光る君へ」を機に、紫式部と越前和紙をつなぐシンボルとして大切にしたいと思う。
(越前市広報R6年7月号)
豪族たちの声 VOL.19
我が家は、もはや山中と言ってよいところにある。庭と境目のない裏山を二階の窓から飽かず眺めている。梅の白い花が咲き始め、ウグイス声に目覚めるようになると、春が近いのを感じて、少しうれしい気分になる。初夏の新緑も暗やみをホタルが流れていく様子も、セミの喧しさも、秋のもみじも、冬の雪化粧も、それぞれに好ましい。
山の上の方には、古墳時代前期(3~4世紀)の松明山古墳がある。発掘調査には祖父ちゃんが人足として加わった。家屋と人物と獣の文様がある鏡や玉の首飾、鉄槍鉋などが出土している。女性司祭者のものだとのこと。
当時、このあたりには地方豪族が割拠していた。大陸の文明も、帰化人たちとともに流れこみ、多文化が交ざりあっていたのだと思う。継体大王が中央に打って出た、その経済的な力、武力があっただろう。和紙も織物も漆器もその頃に始まる物語がある。打刃物も指物も鉄文化や木工のベースがあったはずだ。真柄甚松先生著、「武生盆地の歴史一」に書かれた「山沿いの道」を読みながら、味真野から始まる道沿いの風景を夢想する。
継体大王の時代から500年後、紫式部もやってきた。さらに500年下って戦国時代、この「山沿いの道」は朝倉街道となる。戦国武将が往来したこの道のひとつは、うちの裏山を抜けて河和田へ、そして一乗谷に入ったとされる。
漆黒の裏山の闇をじっと眺めていると、樹齢数百年の杉の大木たちがその姿を浮かび上がらせる。女性司祭者や豪族の声、武人の足音が聞こえてくるようだ。
(越前市広報R6年6月号 やまけんコラムVOL.23)
北陸新幹線県内延伸 VOL.18
3月16日、半世紀の悲願であった北陸新幹線の敦賀までの開業の日を迎えました。朝6時23分の始発のかがやきを越前たけふ駅で見送り、次の列車で追いかけて福井駅で行われたハピラインふくいの開業式典に出席。すぐに、越前たけふ駅にとって返し、越前市の開業式典を開催。そして、11時からは、福井駅前の新しいホテルで県全体の開業祝賀会に参加することができました。
整備計画の決定から50年、歴代の知事や県議会議員、国会議員、経済界をはじめ、多くの方々の大変な努力があり、また、地権者をはじめとする地元のご協力がありました。
越前たけふ駅と福井駅を往復した車窓の景色を眺めながら、新幹線事業に直接携わった私の脳裏には、亡くなられた地元の美濃美雄元県議をはじめ懐かしい顔が去来しました。
県会議員のみなさんが、ハチマキ姿でのぼり旗を持って、連日、政府、与党に対して要望を重ねられたこと、福井駅部800mの「点の認可」を勝ち得た日、そして、敦賀までの認可が実現した時のこと。
しかし、課題は次々と湧いてきます。用地取得の遅れ、生コンの不足、入札の不調、事業費の増嵩など、山のようにありました。こうした課題を一つひとつ解決するための努力があって、この開業という成果に結びついたと思います。
多くの公務員は、努力した仕事の成果を自らが得ることは稀ですが、幸運にも市長という立場で開業の祝賀に参加することができました。その夜には、かつての仲間たちと、苦労話を語り、喜びを分かち合うという幸せな時間を持つこともできました。
また、当時、厳しく議論をぶつけあった鉄道・運輸機構の人が、すでに退職し、プライベートで開業を見に福井に来られていて、偶然お会いし固い握手で、感激を共有しました。
携わったすべての人に、それぞれのプロジェクトXがあり、それが、この奇跡の一日に結実する大きなプロジェクトXを作り上げたのだ、と感じています。そして、開業効果の息の長い持続的な拡大と敦賀以西の大阪までの全通に、総力を結集しなければと、決意を新たにしているところです。
(越前市広報R6年5月号)